生成AIの活用が加速する一方で、著作権や知的財産をめぐるトラブルが世界各地で表面化しています。とくに2025年に入ってからは、大手企業やコンテンツホルダーが法的措置を取る事例が相次ぎ、企業のIT担当者にとって「安全にAIを使うためのルール作り」が急務となっています。
ここでは、最近注目された生成AIと著作権に関するニュースを5件取り上げ、それらが示すリスクを整理した上で、企業が取るべき実践的なガイドラインを提示します。
生成AIと著作権に関する最近のニュース5選
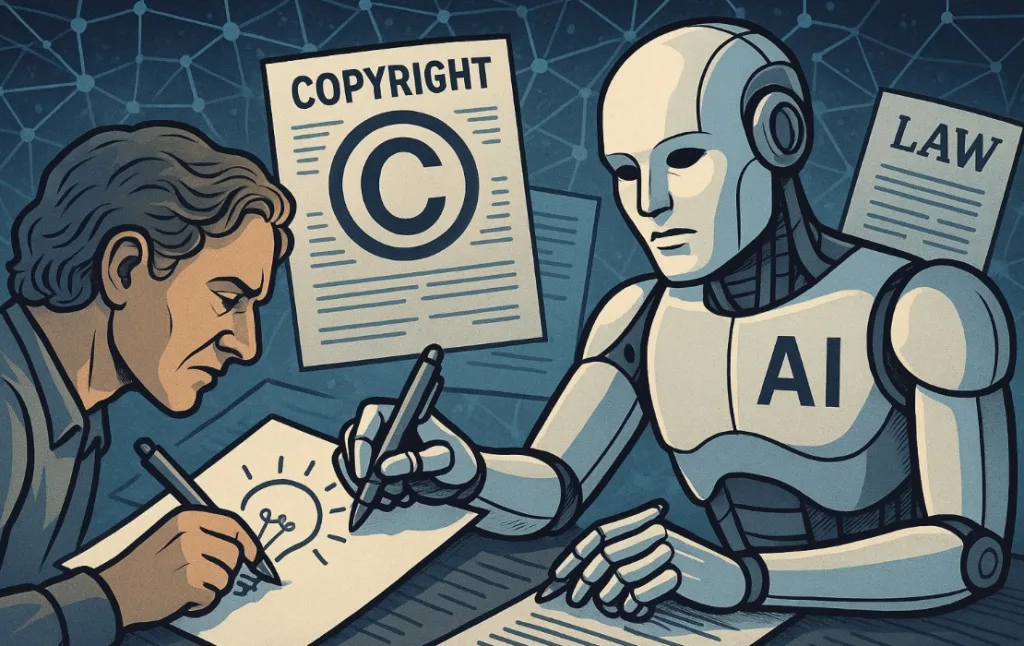
1. Anthropic、著者団体と15億ドルで和解
2025年9月、生成AIモデルClaudeを提供するAnthropicは、米国の著者団体との間で著作権訴訟を和解しました。その額は15億ドル(約2200億円)と巨額です。AIモデルが著作物を無断で学習に使用した点が争点となり、裁判所の承認を経て和解が成立しました。
この件は、モデル提供元がどのようなデータを学習に利用しているのかを透明化することの重要性を示しています。企業が「何を使っているのか分からないAI」を安易に導入すると、二次利用や商用利用で同様のリスクを抱える可能性があります。
2. Warner Bros、Midjourneyを提訴
米Warner Bros Discoveryは、画像生成AI「Midjourney」がスーパーマンやバットマン、バグズ・バニーなど同社の著名キャラクターを無断生成しているとして提訴しました。
キャラクターは企業のブランド資産であり、その価値は計り知れません。こうしたケースは「AIによる著作権キャラクターの模倣」が法廷で争われる初期事例のひとつであり、今後は他のコンテンツホルダーも追随する可能性があります。
3. Disney、Character.AIに警告
2025年9月末、Disneyは生成AIチャットサービスCharacter.AIに対して「ディズニーキャラクターを模倣するチャットボットの利用停止」を正式に警告しました。
ディズニーキャラクターの人格や話し方をAIが模倣することは、著作権や商標権に加え、ブランドイメージの毀損につながるリスクがあります。この事例は「画像や映像」だけでなく「人格的特徴」も知的財産と見なされる動きを象徴しています。
4. 声優による“無断生成AI音声”利用への抗議運動
2024年、日本を代表する声優26名が連名で、生成AIによる無断音声利用に抗議する運動を開始しました。『ドラゴンボール』フリーザ役の中尾隆聖氏や、人気声優の梶裕貴氏らが参加し、自身の声が勝手にAI学習・生成に利用されていることへの懸念を訴えています。
「NOMORE無断生成AI」というスローガンのもと、業界団体や声優本人が啓発活動を展開。法制度の整備や業界内ルールの確立を求める声が強まっています。現時点では訴訟に発展した事例は限られますが、声や演技といった“人格的表現”も権利対象となる流れを示す重要なニュースです。
5. 東映アニメーションによるAI導入計画と訂正
2025年5月、東映アニメーションは決算資料で「絵コンテや背景、美術など制作工程にAIを活用する方針」を示しました。『プリキュア』シリーズを例に、AI活用による制作効率化を検討していることが明らかになり、アニメ業界で大きな波紋を呼びました。
しかし直後に「実際の導入実績はまだない」との訂正も発表され、ファンや業界関係者の誤解を招いたことを認めました。この件は、企業がAI導入を発表する際に構想段階と実運用段階を明確に区別しなければならないことを示しています。効率化とクリエイター保護のバランスをどう取るかが今後の焦点となるでしょう。
生成AIの著作権リスクの種類
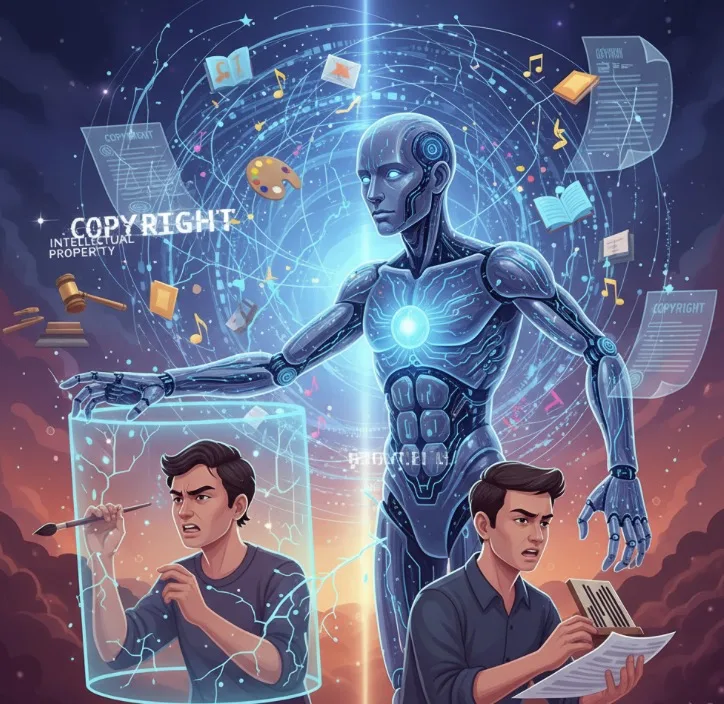
学習データ利用
AIモデルがどのようなデータで訓練されているかが不透明な場合、無断使用された著作物を基にしたモデルを利用してしまうリスクがあります。訴訟や和解の費用はモデル提供企業だけでなく、利用者側のビジネスにも波及します。
生成物の侵害
生成された画像・映像・文章が既存作品と酷似している場合、著作権侵害や商標権侵害に該当する可能性があります。特に企業が外部顧客に納品する場合、二次利用や商用利用の段階で大きな問題となります。
音声・キャラクター模倣
声やキャラクターの人格的特徴をAIが再現することは、著作権に加え、肖像権・パブリシティ権・著作隣接権の侵害リスクを伴います。近年の声優抗議やディズニーの警告は、この領域の危うさを示しています。
企業への影響は?
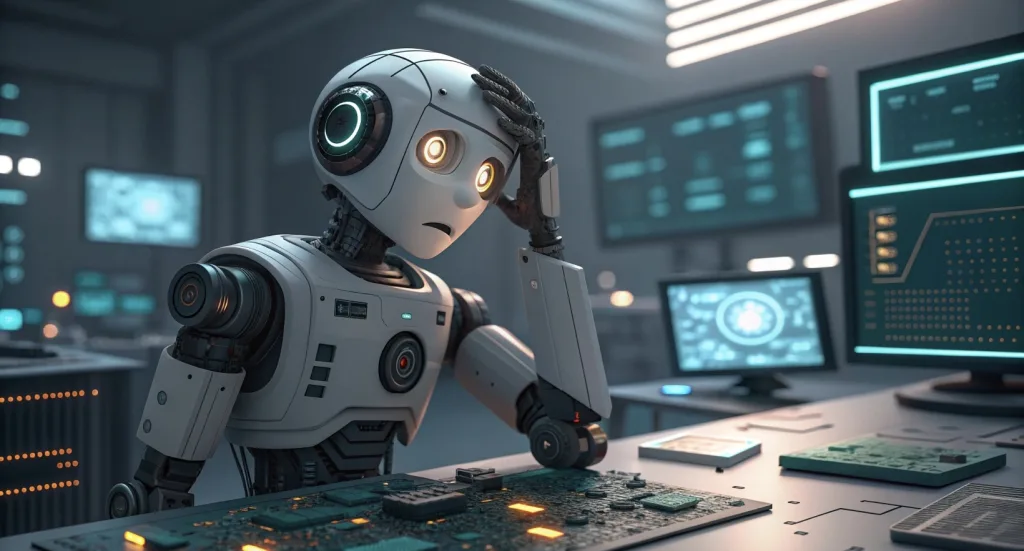
- 社内利用の油断リスク
「社内利用だから安全」とは言えず、社内文書や教育コンテンツに無断利用の要素が含まれると、外部に漏れた際に法的責任を問われる可能性があります。 - 取引先への納品リスク
生成AIで作成した資料やクリエイティブを外部顧客に提供する場合、著作権侵害が判明すれば契約違反や損害賠償につながります。 - 国際展開時の法制度差
米国と日本では著作権法の考え方に違いがあり、海外市場に向けてサービスや製品を展開する企業ほどリスクが増大します。
企業が取るべきガイドライン

利用ポリシー整備
まず社内で「生成AIをどの業務に、どの範囲で利用できるのか」を明文化する必要があります。従業員が独自に使った結果、著作権リスクを抱え込む事態を防ぎます。
契約・ライセンス確認
利用するAIモデルがどのようなデータで訓練されているのか、生成物の商用利用が許可されているかを必ず確認しましょう。ベンダー選定時には透明性のある説明を求めることが重要です。
ツール選定基準
生成AIを比較・導入する際には、著作権対応や安全性への取り組みを公表しているかどうかを基準に加えるべきです。単に精度やコストだけで選定すると、後にリスクを抱え込むことになります。
レビュー体制の導入
生成AIの成果物をそのまま利用せず、必ず人間がチェックする体制を構築してください。法務部門や知財部門と連携し、リスクが高いコンテンツを事前に排除することが不可欠です。
生成AIの著作権リスクに備える:まとめ
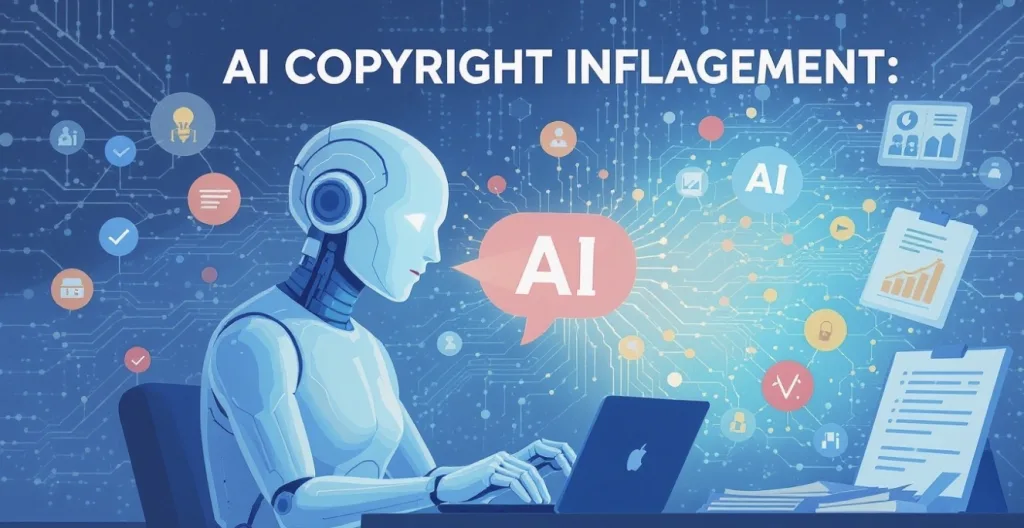
生成AIはビジネスに大きな価値をもたらす一方で、著作権リスクという新たな課題を企業に突きつけています。Anthropicの和解やWarner・Disneyの動き、声優による抗議活動など、ニュースで示された事例は他人事ではありません。
IT担当者としては、社内ポリシー・契約確認・ツール選定・レビュー体制の4点を基盤に、生成AIを「安全に活用する仕組み」を整えることが求められます。適切なガイドラインの整備によって、生成AIを安心して業務に取り入れ、企業価値の向上につなげていきましょう。



