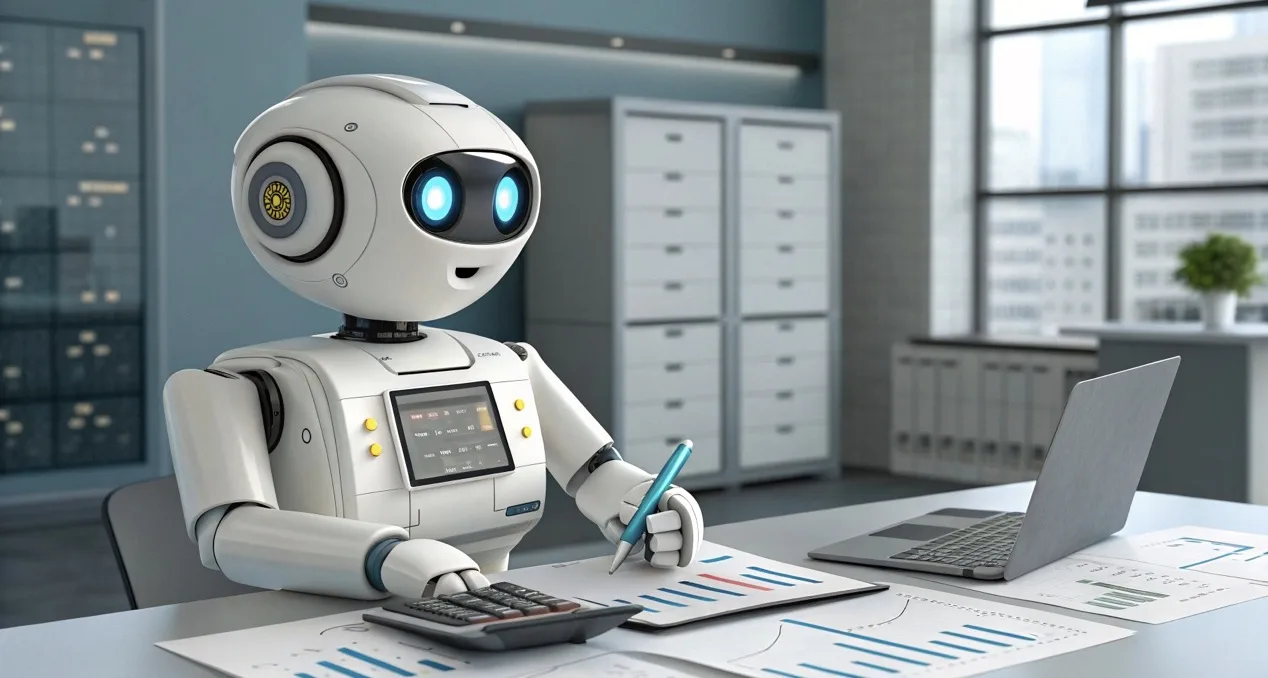本記事では、経理部門で実際に効果を発揮している生成AI活用事例を10選ご紹介します。請求処理から決算支援まで幅広いユースケースを押さえることで、自社導入のヒントとしてご活用ください。
経理部門にも広がる生成AI活用の波

経理部門は、企業活動において欠かせない基盤業務を担っています。請求書処理、経費精算、伝票入力、決算対応など、日々のタスクは膨大かつ正確性が求められるものばかりです。これらの業務は属人化しやすく、繁忙期には経理担当者の負担が集中することが課題となってきました。
近年、生成AIや関連技術の進化により、こうした経理業務にも自動化と効率化の波が押し寄せています。従来はルールベースでしか対応できなかった処理も、生成AIなら柔軟に対応できるようになり、定型処理だけでなく、非定型なやり取りや分析業務にも活用が広がっています。
たとえば、請求書の形式が取引先ごとに異なる場合でも、AIが自動的に読み取り、共通フォーマットに変換できます。また、AIがデータの異常値や不正の兆候を検出することで、内部統制を強化し、経営リスクの軽減にもつながります。
経理業務フロー × AI活用領域(図表)
以下の表は、経理部門の主要業務フローにおいて、AIがどのように活用できるかを整理したものです。業務全体を俯瞰して導入検討を進める際の参考になります。
| 経理業務フロー | AI活用領域 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 請求書受領・処理 | OCR × LLMによるデータ抽出 | 手入力の削減、入力精度の向上 |
| 経費精算 | 領収書画像認識、自動仕訳提案 | 処理時間の短縮、不正検知の強化 |
| 仕訳・伝票入力 | 自然言語処理による仕訳分類 | 属人化の解消、誤入力の防止 |
| 月次決算 | 数値チェック自動化、異常検知 | 早期決算、精度向上 |
| 予実管理・分析 | 生成AIによるレポート生成 | 分析工数の削減、迅速な意思決定支援 |
| 年次決算・監査対応 | 監査資料の自動生成、質問応答 | 監査準備の効率化、担当者負担軽減 |
このように、経理担当者の役割は単なる入力作業から、AIを活用した監督・分析・戦略的判断へとシフトしつつあります。次章では、その具体的な活用事例を10の観点からご紹介します。
経理部門のAI活用事例10選
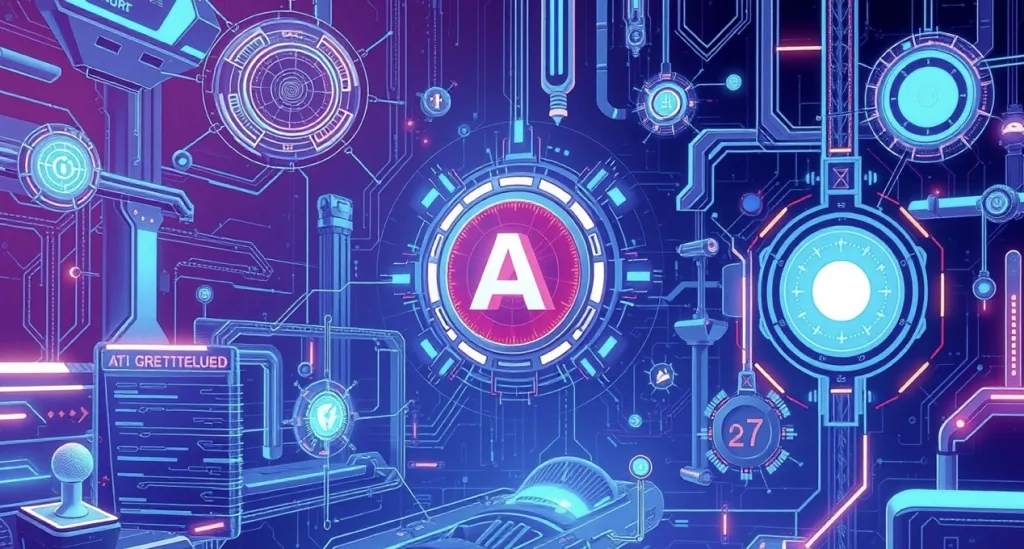
1. 請求書処理の自動化
請求書処理は経理部門において最も工数がかかる業務の一つです。従来は紙やPDFの請求書を人が目視で確認し、会計システムに入力していましたが、これは非常に時間がかかり、入力ミスも避けられません。生成AIをOCRと組み合わせれば、請求書の金額・日付・取引先名などを自動で読み取り、仕訳データとして整形できます。
さらに、過去の仕訳ルールを学習しているAIなら、勘定科目を自動提案し、担当者は確認と承認に専念できるのです。これにより、請求処理のスピードが大幅に向上し、ヒューマンエラーも削減されます。
2. 経費精算の効率化
出張や接待で発生する経費精算も、担当者にとって負担が大きい業務です。領収書を確認し、規程に従って承認・却下を判断する作業は煩雑で、違反や不正利用の温床となることもあります。生成AIを導入すれば領収書画像を読み取り、自動的に経費規程に照らして判定できます。
たとえば「深夜タクシー代」「高額接待費」といった規程外のケースを検知してアラートを出すことも可能です。これにより担当者の確認作業が効率化され、不正防止にも寄与します。
3. 伝票入力・仕訳作業の自動補助
伝票入力や仕訳作業は経理業務の基本ですが、反復作業が多く、ミスが起こりやすい領域でもあります。AIは過去の仕訳データや会計基準を学習し、勘定科目や金額処理を自動で提案できます。
これにより、担当者は「承認・修正」に注力できるようになり、全体の処理スピードが大幅に向上します。さらにAIがエラー検出を行うため、仕訳の整合性チェックにも効果を発揮します。

4. 支払予定表の作成支援
キャッシュフロー管理において、支払予定表は非常に重要です。従来はエクセルなどで手作業により集計していましたが、AIは契約条件や請求書データをもとに自動で支払予定表を作成できます。
支払期日が近いものを優先的に整理したり、支払傾向を分析して将来の資金繰り予測を行ったりすることも可能です。これにより、経理部門は経営層へ迅速かつ正確な情報提供ができるようになります。
5. 売掛金管理と入金消込の自動化
売掛金管理や入金消込は、金額の突合や差異の確認が煩雑で時間を要します。生成AIを使えば入金データと請求データを照合し、不一致を即座に検出できます。
さらに未回収債権の一覧を自動生成し、取引先ごとの遅延傾向を分析することも可能です。これにより回収業務の優先順位をつけやすくなり、未回収リスクを低減できます。
6. 決算資料作成の自動支援
月次や四半期、年度決算の資料作成は膨大なデータ処理を伴います。AIを活用すれば、会計システムからデータを自動で収集・整理し、試算表や決算書のドラフトを短時間で作成できます。
さらに、勘定科目ごとの異常値や前年同期比の大幅変動なども自動で検知できるため、監査対応の準備が効率化されます。経理担当者は数字の裏にある要因分析に集中できるため、経理部門の付加価値が高まります。

7. 税務関連ドキュメントの作成補助
税務申告や関連書類の作成は専門性が高く、法改正にも迅速に対応する必要があります。生成AIは最新の税制改正情報や過去の申告データを参照し、必要な記載項目を自動でチェックします。
また、誤りや抜け漏れをアラートで示すことも可能です。最終的な判断は専門家が行いますが、AIを補助として活用することで、準備時間の短縮と精度の向上が両立できます。
8. 契約書・取引条件チェック
契約書の中には、経理に大きく影響する支払い条件や違約条項が含まれます。AIは契約書を解析し、リスクが高い条件や過去取引との不整合を指摘できます。
たとえば支払期日の一方的な変更や、相場に合わない違約金条件を自動で検出し、担当者に注意を促します。これにより契約リスクを事前に把握し、企業全体のリスクマネジメントを強化できます。
9. 内部統制と不正検知
経理データをAIで分析すると、人間が気づきにくいパターンや不正の兆候を検出できます。特定の取引先に集中する支払や、分割して行われる異常な取引など、不自然な動きを自動で洗い出せます。
これにより内部監査が効率化され、不正の早期発見につながります。従来は事後対応が多かった不正検知を、AI活用により「予防型」へと転換できるのです。
10. 経営分析・レポート作成
経理部門は企業の財務データを最も多く扱うため、経営層への情報提供に直結します。AIは収益構造やコスト構造を自動で分析し、グラフやレポートとして可視化します。
これにより、経営層は迅速に意思決定ができ、経理部門は「数字を出す部署」から「戦略提言を行う部署」へと進化できます。
導入における注意点

生成AIを経理部門に導入する際には、以下のポイントを押さえておく必要があります。
- データ品質の確保:入力データが正確でなければ、AIの出力も誤る
- 人間の確認プロセス:AIの提案を鵜呑みにせず、最終判断は必ず担当者が行う
- セキュリティ・コンプライアンス遵守:機密情報の取り扱いや税法規制に違反しない運用ルールの徹底
- 小規模導入からのスタート:まずは限定的な業務で効果を確認し、徐々に範囲を拡大
経理業務に強い生成AIツール3選

ChatGPT(GPT-5/oシリーズ)
OpenAIのChatGPTは、請求処理や仕訳提案、契約書チェックなど幅広く対応可能です。API連携により会計システムとの統合も進めやすく、企業利用に適しています。
Microsoft Copilot for Finance
MicrosoftのCopilotシリーズの一部で、ExcelやDynamics 365と統合。仕訳の自動提案や経費精算の効率化に強みがあり、既存のMicrosoft環境を活かした導入が可能です。
freee AIアシスタント
クラウド会計ソフトfreeeに搭載されたAIアシスタントは、日本の税制や会計処理に特化。請求書作成から決算支援まで一貫したサポートができ、中小企業やスタートアップでの導入実績が豊富です。
経理部門における生成AI活用:まとめ

経理部門における生成AI活用は、請求処理や決算支援といった定型業務を効率化するだけでなく、不正検知や経営分析といった高度業務へも拡大しています。これにより経理担当者は、単なる処理業務から「経営を支える情報分析役」へと役割を広げつつあります。
企業のIT担当者は、小さく始めて効果を検証しながら導入範囲を広げることが重要です。経理業務に強い生成AIをうまく活用すれば、部門の負担軽減だけでなく、企業全体の意思決定スピードを高める原動力になるでしょう。