業務効率化の手段として、多くの企業で導入が進んだのがRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)です。定型業務を自動化し、人的リソースをより創造的な業務へと振り分ける動きは、すでに広く浸透しています。
そこに新たな選択肢として登場したのが生成AIです。文章や画像を生み出す能力を持ち、従来のRPAでは対応できなかった非定型業務の効率化を可能にしました。しかし、「RPAと生成AIのどちらを導入すべきか」と迷う企業も少なくありません。本記事では、RPAと生成AIの違いと特性を整理したうえで、実際の業務にどう使い分け、組み合わせていくべきかを解説します。
生成AIとRPAの違い
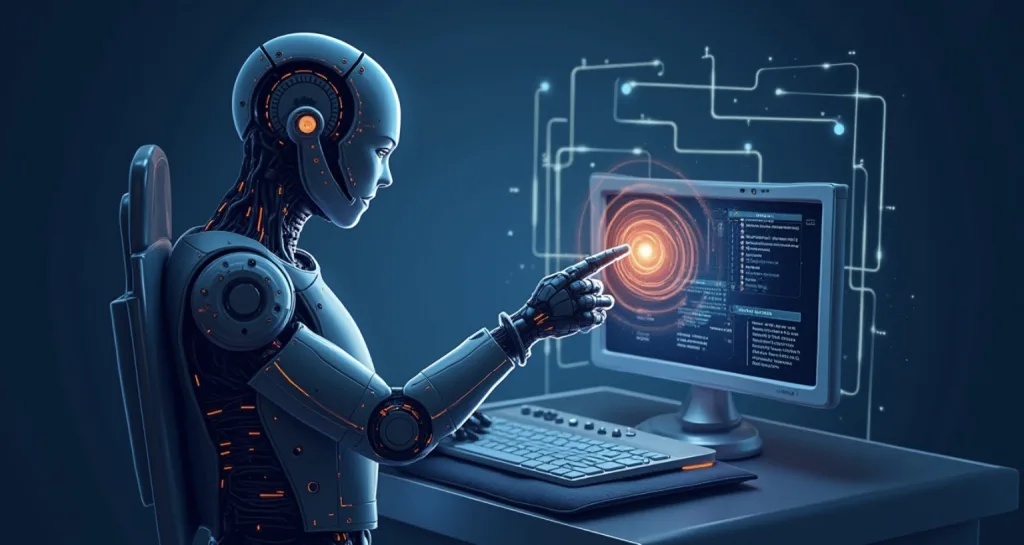
RPAとは何か
RPAとは、パソコン上で人間が行っている定型作業を自動化する仕組みを指します。たとえば、請求書データをシステムに転記する、受注データを基幹システムに登録するといった業務を、人の代わりにソフトウェアロボットが実行します。RPAはルールベースで動作するため、手順が明確に定義されている処理に強みを発揮します。
一方で、例外処理や入力データのばらつきに弱いという課題があります。複雑な条件分岐や文脈理解を必要とする場面では誤作動を起こす可能性が高く、運用管理にコストがかかるのも事実です。つまりRPAは「決まったことを正確に繰り返す」領域では非常に強力ですが、柔軟性には限界があります。
生成AIとは何か
生成AIは、大量のデータを学習したAIモデルが文章や画像を生成する技術です。従来のAIが「判断」や「分類」に強かったのに対し、生成AIは新しいコンテンツを生み出す能力を持っています。具体的には、顧客からの問い合わせに対して回答文を作成する、議事録を自動要約する、あるいはデータから洞察を抽出して改善提案を提示するといった応用が可能です。
その強みは「曖昧さ」や「非定型」に対応できる点にあります。たとえば、文章のニュアンスを読み取り、自然な言葉で書き換えるといった処理はRPAでは難しく、生成AIならではの領域です。ただし、精度や信頼性の課題が残ることも事実であり、誤情報を出力するリスクや、データ管理・セキュリティ上の注意が不可欠です。
RPAと生成AIの違いを整理
| 観点 | RPA | 生成AI |
|---|---|---|
| 自動化の対象 | 定型業務、ルール化可能な手順 | 非定型業務、曖昧さを含む処理 |
| 強み | 正確さ、処理速度 | 柔軟さ、文章生成や要約 |
| 弱み | 例外処理に弱い、開発工数が必要 | 精度や信頼性にばらつき、セキュリティ懸念 |
| 導入のしやすさ | ツールによっては容易、ただし設定が必要 | クラウドサービス利用で手軽に導入可能 |
| 主な利用シーン | 経理処理、受発注管理、システム間データ連携 | FAQ対応、議事録要約、レポート生成 |
このように、両者は「競合」ではなく「補完関係」にあります。
効果的な使い分けと組み合わせ方

RPAと生成AIは、得意分野が明確に異なるため「役割分担」を意識することが重要です。RPAはルールが明確な業務を自動化することで土台を作り、生成AIはその土台の上で柔軟な判断やコンテンツ生成を担うという補完関係を築けます。
1. 部門ごとの使い分け
- 経理・財務
RPAで請求書や伝票入力、支払い処理を自動化。一方、生成AIは経理データを分析して「異常値の可能性」「コスト削減の提案」といったインサイトを提示できます。 - 人事・総務
RPAで勤怠管理や社員情報の更新を行い、生成AIで従業員アンケートを要約し、人事施策の改善ポイントを抽出。 - 営業・マーケティング
RPAでリード情報をCRMへ登録、スケジュール調整メールを自動送信。生成AIは顧客との過去のやり取りを分析し、最適な提案文を作成。 - カスタマーサポート
RPAで定型的な問い合わせ(配送状況確認など)に即応し、生成AIで複雑な質問に自然な文章で回答を生成。
2. プロセス全体での組み合わせ
1つの業務フローにRPAと生成AIを組み合わせることで、シームレスな自動化を実現できます。
- 例:レポート作成業務
RPAが基幹システムからデータを収集 → 生成AIがデータを要約・文章化 → RPAが定められたフォーマットでファイルを保存・共有。 - 例:契約審査業務
RPAが契約書をOCRで読み込みシステムに登録 → 生成AIが内容を要約し、リスクや不足事項をコメント → RPAがレビュー依頼を担当者に送信。
3. 戦略的な導入ステップ
- 第一段階:RPAで業務の基盤を固める
標準化・定型化できる業務をRPAで効率化し、安定したオペレーションを確立。 - 第二段階:生成AIで付加価値を生む
業務改善提案やレポート要約など、判断や文章化を必要とする領域に生成AIを活用。 - 第三段階:統合運用でインテリジェント化
RPAと生成AIを同じ業務プロセスに組み込み、意思決定から実行までを自動化する「インテリジェントオートメーション」を目指す。
導入・運用の注意点
RPAと生成AIのいずれを導入する場合も、いくつかの注意点があります。
- ガバナンスとセキュリティ
生成AIは外部サービスを利用するケースが多いため、機密データの取り扱いには十分な配慮が必要です。RPAについてもアクセス権限の管理が重要です。 - 社内教育と利用ルール
導入しても現場社員が使いこなせなければ効果は限定的です。生成AIではプロンプト設計のトレーニングが有効であり、RPAでは基本的なシナリオ作成スキルが求められます。 - 「どちらか」ではなく「組み合わせ」を前提にする
どちらの技術も万能ではありません。RPAと生成AIを組み合わせ、業務特性に応じて最適化する視点が重要です。
生成AIとRPAの違いと使い分け:まとめ
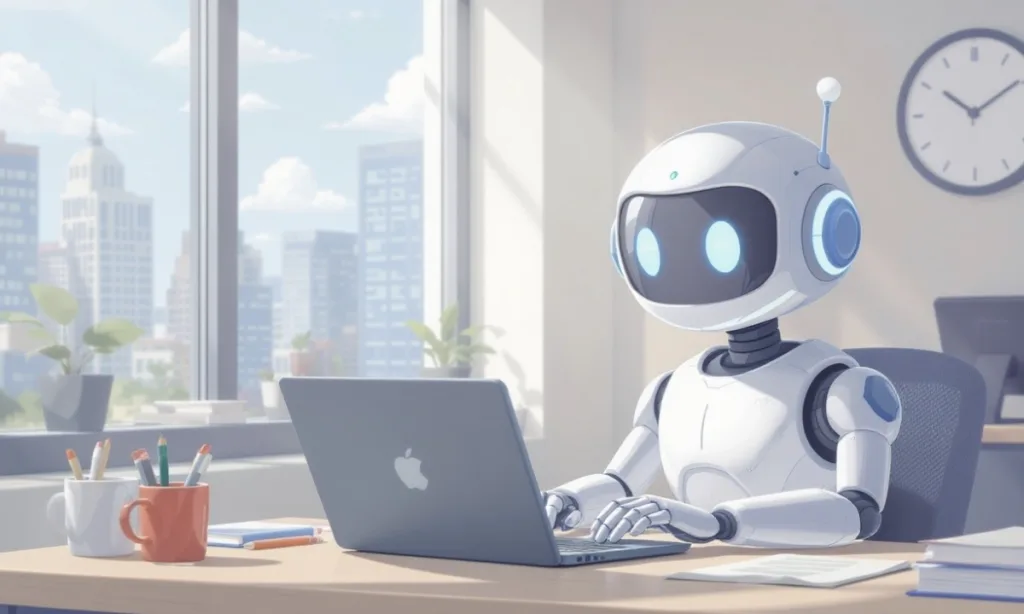
RPAと生成AIは、ともに業務効率化のための強力な手段ですが、その性質は大きく異なります。RPAは定型業務を確実に処理する「基盤」であり、生成AIは非定型業務を補完し、柔軟性を与える「拡張」です。両者を競合させるのではなく、戦略的に組み合わせることで、企業は業務効率化を一段高いレベルに引き上げることができます。
IT担当者に求められるのは、「自動化の設計者」として両者の特性を理解し、業務に最適なシナリオを描くことです。RPAで安定した業務基盤を作り、生成AIで柔軟な付加価値を生み出す。その組み合わせこそが、これからの業務効率化の最新ベストプラクティスと言えるでしょう。



