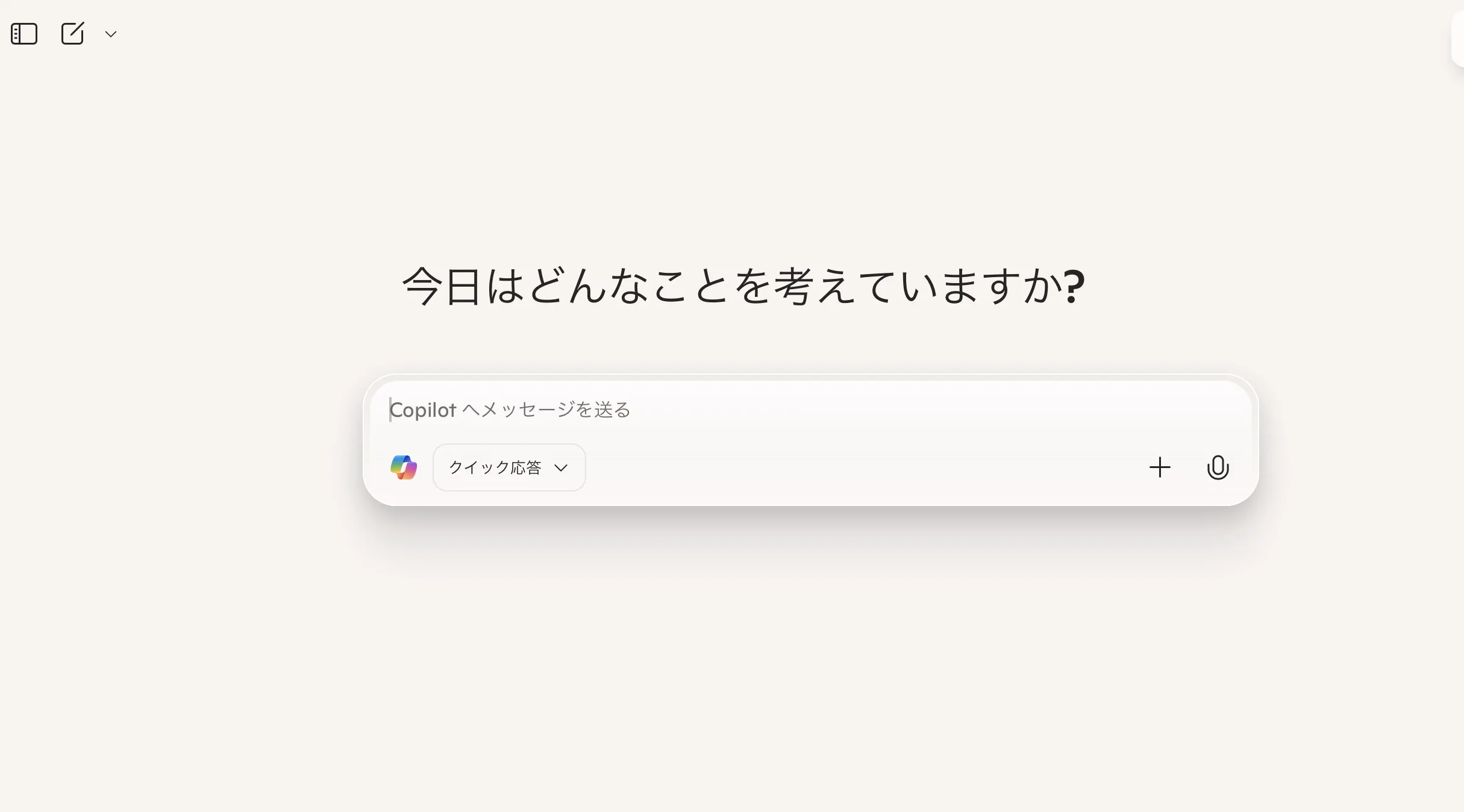人手不足の深刻化や業務の属人化に直面する企業にとって、Microsoft Copilotの導入は救世主のように映ります。業務効率化と生産性向上を約束するこのAIツールは確かに魅力的ですが、その陰に潜む情報漏洩リスクは見過ごされがちです。便利さの裏側には、適切な管理がなければ企業の機密情報を危険にさらす可能性が隠れています。
この記事では、Copilotを企業で導入する際にとくに注意すべき5つの情報漏洩リスクと対策を中心に、具体的な“落とし穴”の事例とともにご紹介します。

この記事の内容は上記のGPTマスター放送室でわかりやすく音声で解説しています。
Copilotの強み:他の生成AIとの比較から見えるメリット

① 企業向け生成AIの5大比較
MiraLabによる比較では、ChatGPT、Gemini、Claude、Grokに加え、Copilotは「Microsoft 365との統合度」が最大の特徴で、日常業務に直接沿ったAIアシスタントと評価されています。
- ChatGPT:推論力と多機能性に優れた汎用AI
- Gemini:長文読解やPDF解析など、文書処理に強みを持つAI
- Claude:自然な日本語生成と長文理解に秀でたAI
- Copilot:Microsoft 365アプリに完全統合された業務特化型AI
② 社内利用でのセキュリティ・運用性
別の比較でも、ChatGPTとGeminiよりもCopilotはMicrosoft 365を既に導入している企業にとって導入・管理がしやすいと指摘されています 。とくにSSO管理、アクセス制御、監査ログ機能など、既存体制との親和性が高い点が評価されています。
Copilotは「既存Microsoft 365環境との親和性」と「情報セキュリティ体制の整備が行いやすい」点から、多くの日本企業にとって導入しやすいソリューションとなっています。
情報漏洩を防ぐために知っておくべき5つのポイント

他の生成AIよりも企業導入しやすいCopilotですが、情報漏洩に関してまったく危険がないわけではありません。より安全にCopilotを使うために以下の5つのポイントを押さえておきましょう。
1.社内データへのアクセス範囲管理の盲点
Copilotの最大の強みは、Microsoft 365環境内の膨大な社内データ(SharePoint、OneDrive、Outlook、Teamsなど)を横断的に活用できる点にあります。しかし、この強力な機能は同時に重大なセキュリティリスクをもたらします。
具体的なリスク事例として、部門限定で共有されていた機密資料の内容が、Copilotの回答生成を通じて他部門の社員に漏れてしまうケースが考えられます。これは従来のアクセス制御の概念を超えた、AIツール特有の情報漏洩経路です。
対策
事前にファイル共有やアクセス制御の見直しを行い「Copilotに読ませてもよいデータ範囲」を社内で定義しておくことが重要です。
2. プロンプト入力によるうっかり情報流出
Copilotは自然言語で指示を与えるAIです。そのため、社員がうっかり機密情報を含んだ形で入力してしまうリスクがあります。
たとえば、「今度のA社との契約書にある非公開の取引額を要約して」と入力した場合、その内容はCopilotの出力やログに記録され、場合によっては他のプロンプトに影響を及ぼす可能性もあります。
対策
「AIに入力してよい情報・してはいけない情報」を明文化したガイドラインを整備し、利用者への定期的な教育を実施することが不可欠です。

3. 生成コンテンツの鵜呑みによる二次的な情報漏洩
Copilotは既存の社内情報をもとに文章を生成しますが、その内容が常に正確とは限りません。また、曖昧なプロンプトに対して推測を含んだ内容を出力することもあります。
このような出力をチェックせず、そのまま社外に提出したり、社内資料に引用してしまうと、誤った情報や機密事項が外部に流出するといった情報漏洩につながる危険があります。
対策
Copilotが生成した文章は必ず人の目でチェックし、正確性と公開範囲を確認してから使用する運用ルールを徹底しましょう。
4. ログの取得・活用が不十分なまま運用が進行
Copilotの導入初期によくある“落とし穴”が、利用ログや操作履歴を記録していないことです。問題が発生しても「誰が・何を・いつ入力したか」が分からず、原因究明や責任の所在を特定できない事態に陥る可能性があります。
対策
Microsoft 365の監査ログやDefender for Cloud Appsなどを活用し、Copilotの利用履歴を自動的に記録・分析できる体制を整備しておきましょう。情報漏洩の兆候を早期に察知可能になります。
5. “とりあえず全社導入”によるルールなき利用拡大
Copilotは多機能で直感的に使えるため、「とりあえず全社で導入してみよう」という意思決定がなされがちです。しかし、ユースケースごとのセキュリティ要件や適合性を無視して導入を拡大すると、想定外の情報漏洩を引き起こすリスクがあります。
たとえば、法務部や経理部など、扱う情報の機密性が高い部門において、十分な検証やガイドラインなしにCopilotを使わせるのは危険です。
対策
まずは影響範囲の少ない部門・業務から段階的にCopilotを導入し、リスクや運用方法を検証した上で、全社展開するのが安全です。
Copilotは便利なツール。しかし「便利さの裏にあるリスク」を見逃さないこと

Copilotは、業務の自動化・効率化を進めるうえで非常に強力なツールです。とくにドキュメント作成やナレッジ検索といった定型作業においては、導入直後から目に見える成果を出すことが可能です。
しかしその一方で、Copilotを正しく制御しなければ情報漏洩を引き起こしかねない“落とし穴”がいくつも存在します。便利さだけに目を奪われず、次の3点を意識することが、Copilotを企業で安全に運用するカギになります。
- 情報管理体制の見直し(アクセス権、共有設定など)
- 利用者への教育とガイドライン整備
- 監査ログなどの仕組みを使ったモニタリング体制の構築
まとめ:Copilot導入は「セキュリティの設計」から始める

AIアシスタントCopilotは、企業の業務変革を支える大きな武器になりますが、その導入は単なる技術導入ではなく「セキュリティ設計を伴う経営判断」でもあります。
情報漏洩という重大なリスクを回避しながら、安心してCopilotを活用するために、いま一度「どんな落とし穴が存在するのか」「それをどう防ぐのか」を企業全体で共有し、備えていくことが求められています。
安全なCopilot活用が実現すれば、AIの力を最大限に引き出しながら、ビジネスの競争力をさらに高めていくことができるでしょう。