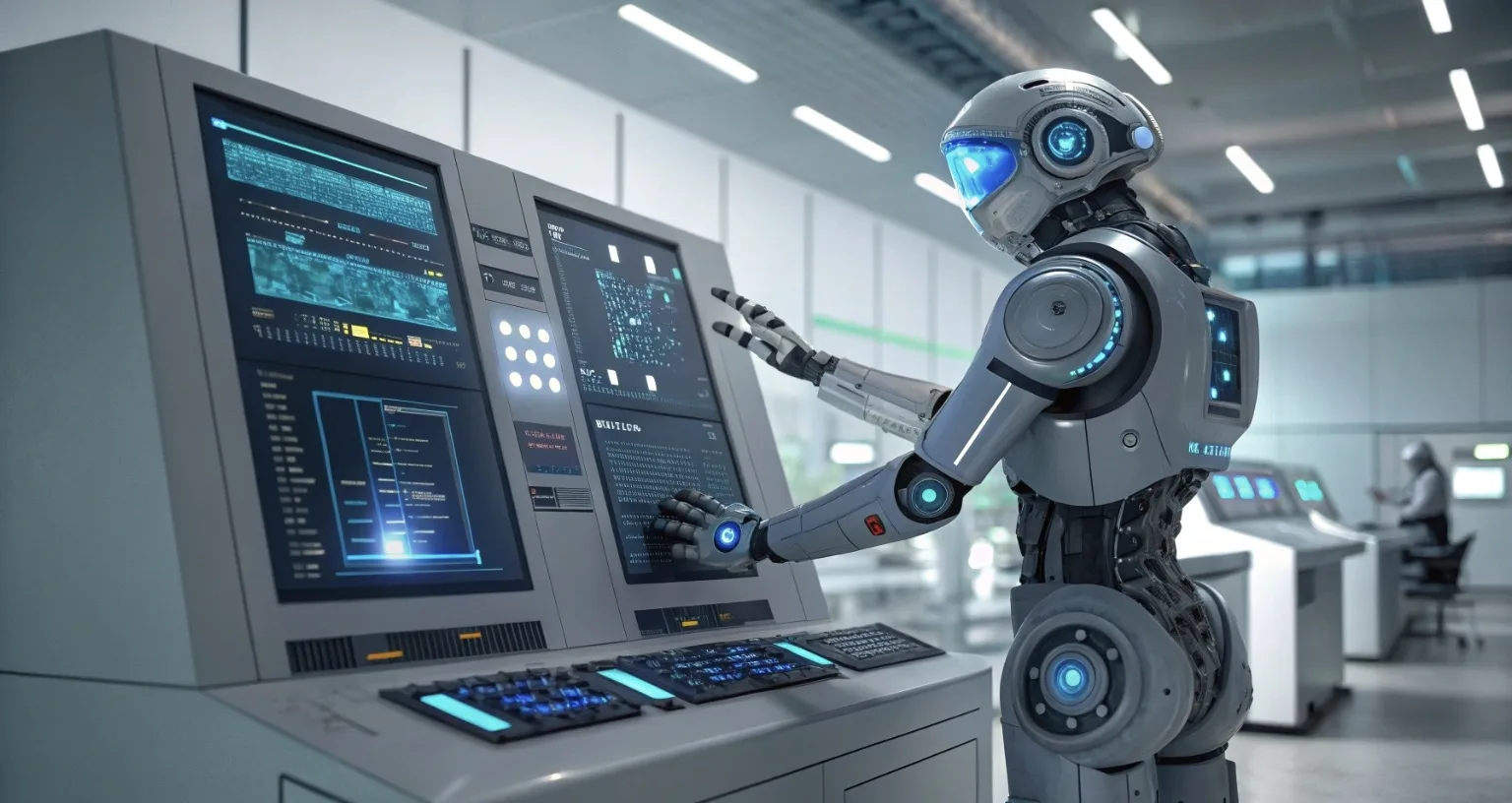生成AIの導入は、いまや多くの企業にとって避けて通れないテーマです。PoC(概念実証)を実施し、社内で小さな成果を積み重ねる企業も増えています。しかし,実際に全社規模での展開を検討すると「既存システムとの統合」という大きな壁に直面するケースが多いです。
ERP、CRM、人事システム、基幹業務システムなど、企業には長年使い続けてきたシステムが存在します。AIを部分的に導入しても、それらと十分に連携できなければ業務全体の効率化にはつながりません。むしろ「新しいシステムが孤立する」「管理コストが増える」といった逆効果になるリスクすらあります。
本記事では、AIと既存システムを統合する際にとくに重要となる5つの課題を整理し、IT担当者が押さえておくべき実践的な視点を紹介します。
課題1:データ形式とAPIの非互換性
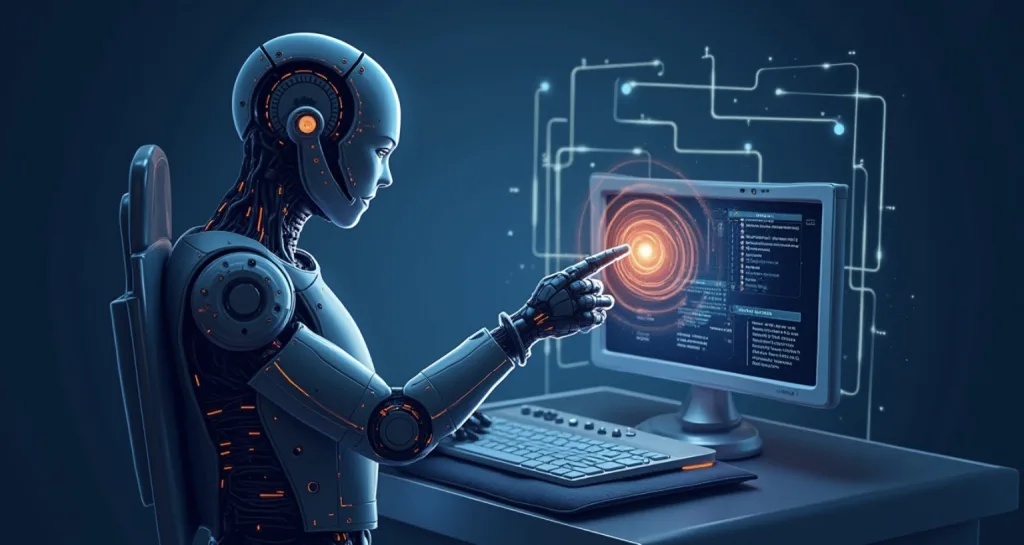
AIを既存システムに統合する際、最初に直面するのが「データ形式の違い」です。
- ERPやCRMは独自のデータ構造を持っている
- 古いシステムではAPIが提供されていない、もしくはSOAP形式など古い仕様に依存している
- クラウドサービス同士でも、JSONやCSVなどフォーマットの違いが障害になる
結果として、AIに必要なデータを取り出せない、あるいは適切な形で学習・参照させられない状況が発生します。
解決の方向性
- APIゲートウェイを導入し、形式の異なるデータを一元的に扱えるようにする
- ETL/ELTツールを活用し、抽出・変換・ロードのプロセスを自動化する
- RAG(Retrieval Augmented Generation)の仕組みを導入し、構造化データや文書をAIに適切に参照させる
課題2:セキュリティと権限管理の複雑さ

AIが社内システムにアクセスする際、もっとも重要なのがセキュリティです。
- 個人情報や機密データが外部に流出するリスク
- 権限のないユーザーがAI経由で情報にアクセスしてしまう危険
- 外部クラウドサービスを経由する際の通信経路の安全性
とくにAIは自然言語での問い合わせに対応するため、通常のシステム利用では想定されなかった情報の引き出し方が起きやすいという特徴があります。
解決の方向性
- ゼロトラストアーキテクチャを前提にした権限設計
- AIが参照できるデータ範囲を明確に制御するアクセス制御リスト(ACL)の整備
- 監査ログの取得・可視化による不正利用の早期発見
課題3:リアルタイム性とバッチ処理のギャップ

既存システムの多くはバッチ処理を前提にしています。日次や週次でデータを集計するERPや会計システムに、リアルタイム処理を前提とするAIを統合するとギャップが生じます。
- AIは「最新データに基づく回答」を期待される
- しかし基幹システムのデータは更新サイクルが遅い
- 結果として「現場の認識とAIの出力がズレる」事態が起きやすい
解決の方向性
- ストリーミング処理基盤(Kafkaなど)を導入し、重要データをリアルタイムで連携
- 必要に応じてキャッシュ機構を組み込み、レスポンスの高速化と整合性の両立を図る
- 全てをリアルタイム化するのではなく、用途に応じて更新頻度を設計する
課題4:コストとパフォーマンスの最適化

AI統合はシステムの複雑化を招き、コスト増加につながるリスクがあります。
- API連携やデータ変換に追加のインフラが必要
- モデル利用のトークン課金が想定以上に膨らむ
- サーバー負荷が増加し、既存システムのパフォーマンス低下を招く
これらはPoC段階では見えにくく、本格運用に移った瞬間に問題化します。
解決の方向性
- 利用頻度に応じたモデル選択(軽量モデルと高性能モデルを使い分ける)
- モニタリングツールで利用状況を可視化し、ボトルネックを早期特定
- 予算内で運用できるよう、コスト試算とシナリオ分析を導入前に実施
課題5:運用体制とガバナンスの整備

AIを既存システムに統合することは、一度つなげて終わりではありません。
- AIモデルのバージョンアップに伴う互換性問題
- システム変更時の影響範囲の把握
- 継続的なセキュリティ監査やコンプライアンス対応
こうした運用課題を見落とすと、「導入したものの維持できない」という結果を招きかねません。
解決の方向性
- AI導入ガバナンスチームを組織し、定期的にレビューや監査を実施
- モデル管理とデプロイ戦略を明確化(MLops/LLMopsの導入)
- システム変更や機能追加を見越した中長期のロードマップを作成
まとめ:統合の成否がAI導入の成果を左右する

AI導入を成功させる鍵は、単なる「モデル選び」や「PoCでの成功」ではありません。既存システムとの統合設計こそが、現場での実効性とROIを決定づける要因です。
- データ形式やAPIの違い
- セキュリティと権限管理
- リアルタイム処理とのギャップ
- コストとパフォーマンス
- 運用ガバナンス
これら5つの課題を事前に把握し、解決策を講じることが、IT担当者に求められる重要な役割です。生成AIの活用はもはや一過性のトレンドではなく、企業競争力を左右する基盤技術となっています。だからこそ「統合の壁」をどう乗り越えるかが、AI活用の成否を決める最大のポイントなのです。