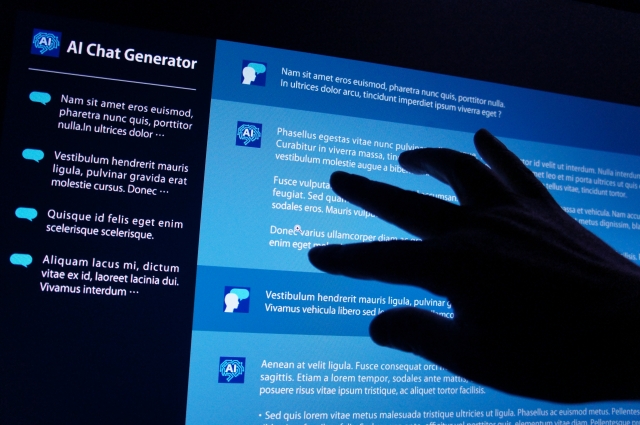企業でChatGPTを活用する際には、当然ながら利用規約を厳守しなければなりません。しかし、「知っておかなければならないこと」とはいえ、利用規約を隅から隅まで熟読するのはなかなか骨の折れる作業ではないでしょうか。
この記事ではOPenAIが公開している利用規約の中から、企業がChatGPTを活用する際にとくに「気をつけるべきポイント」をまとめたので、是非一読ください。ここで触れたものを押さえておけば、間違った使い方はしないで済むようになります。
OpenAIによるChatGPTの利用規約は全部で9章

ChatGPTの利用規約の原文は、OpenAIのサイトのこちらで確認できます。全部で9章から成り立つ利用規約の中から、企業で利用する際にとくに重要と思われるものをピックアップします。
ChatGPTの使用に関する制限

利用規約の第2章には、ChatGPTの使用に関する制限が記載されています。重要な部分をまとめると以下のとおりです。
- 不正目的、犯罪行為を目的とする使用は禁止
- OpenAIの事前同意なしに API キーの売買または譲渡は禁止
- 著作権などの知的財産権を侵害する使用は禁止
不正や犯罪行為を目的とした使用は当然ながら禁止されています。また、簡単に取得できるAPIキーですが、APIキーの売買や譲渡は禁止です。著作権に関する部分はやや複雑なので、詳しくは以下の記事をご覧ください。
出力したコンテンツの商業利用が可能

利用規約の第3章には、ChatGPTが出力したコンテンツへの扱いが主に書かれています。押さえるべきポイントは以下のとおりです。
- ChatGPTが出力したコンテンツの著作権は利用者に譲渡される
- 出力されたコンテンツの正確性は保証されていない
つまり、ChatGPTが出力したコンテンツは商業利用が可能です。ただし、出力された情報が本当に正しいかどうかは保証されていません。企業という立場で情報をリリースする場合、情報の正確性を確認する必要があります。
入力したコンテンツは学習される可能性がある
同じくChatGPTの利用規約第3章には、以下のような記載があります。

上記の文章を要約すると「APIを利用せずに入力したコンテンツは、OpenAIの開発や改善に利用する可能性がある」ということです。つまり、ChatGPTに個人情報や社内の機密情報を入力してしまうと、それらの情報が漏洩してしまう可能性があります。
情報漏洩を防ぐためにはAPIの利用またはオプトアウトの申請を行うことです。そうすればChatGPTが入力したコンテンツを学習することはありません。企業でChatGPTを利用する際には、いずれかの対処を行うのが望ましいです。オプトアウト申請については以下の記事をご覧ください。
著作権を侵害された時の対処法

著作権に関しては、加害者ではなく被害者になってしまう可能性もあります。利用規約の9章にはもしも自分達の著作権が侵害されていると感じた時のための、申告フォームが案内されています。
まとめ:企業で活用するのなら企業用のChatGPTの導入を検討

ChatGPTは企業で利用するも、非常に便利なツールです。しかし、定められたルールがある以上、それらは厳守しなければなりません。また、情報漏洩や著作権など自分達で守らなければならないものもあるのが大きなポイントです。
企業でChatGPTを活用するのであれば、企業用に設計されたChatGPT Enterpriseがおすすめです。私たちGPT Masterでは企業のChatGPT導入ならびChatGPT Enterpriseの導入を支援を行っています。お気軽にご相談ください。
なお、企業用のChatGPT Enterpriseに関しては、以下の記事で詳細を確認できます。