2025年下半期、企業にとってAIは欠かせない存在となりました。しかし同時に、リスクの複雑化と高度化が進み、従来の情報セキュリティだけでは対応しきれない状況が広がっています。生成AIの急速な普及は業務効率化をもたらす一方で、ディープフェイク詐欺やインサイダー脅威の増加といった新たな課題を引き起こしています。
企業のIT担当者やAI推進リーダーに求められるのは、単なる防御ではなく「リスクを前提にAIをどう活かすか」という発想です。本記事では、2025年下半期に注目すべきAIリスクマネジメントの最新トレンドを整理し、実務で役立つポイントを解説します。
AI規制・ガバナンス 2025年下半期の最新動向

EU AI法の適用段階(2025年8月)
2025年8月2日から、EU AI法におけるGPAI(ゼネラルパーパスAI)向けの透明性・著作権対応などの義務が適用開始となりました。既に市場に出ているモデルには猶予があり、2027年8月2日までに適合が求められます。
また、任意の「GPAIコード・オブ・プラクティス」が2025年7月10日に公表され、実務対応の手がかりが整理されました(義務ではありません)。欧州拠点やEU市場を対象とする日本企業は、導入時点でのリスク評価を含むガバナンス設計を前提にした対応が要ります。
中国におけるAI安全規制
中国では、深度合成(ディープフェイク等)規則(2023年1月10日施行)や生成AIサービス暫定管理弁法(2023年8月15日施行)が既に運用されており、安全性評価やアルゴリズム届出、不適切コンテンツ抑止などへの適合が求められます。「導入されつつある」ではなく、すでに規制が施行・運用されている点に留意してください。
日本企業への影響
国内でも経産省・総務省の「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」(2025年3月公表)が整備され、自主的なAIガバナンスの実務が具体化しました。個人情報保護との整合を図りつつ、**「規制対応=コスト」ではなく「規制対応=信頼構築」**の視点で、社内方針とエビデンスの整備を進めてください。
高度化するサイバーリスクと防御戦略

AIを活用した攻撃の拡大
攻撃者はAIを偵察・フィッシング文面作成・情報要約などに利用し、作戦サイクルを短縮しています。2025年版DBIRでもシステム侵入や脆弱性悪用の比重増大が指摘され、インシデント22,052件/漏洩12,195件という最大規模のデータで傾向が示されています。
シグネチャ前提の静的防御だけではなく、AIを用いた脅威インテリジェンスと検知自動化の併用が不可欠です。
インサイダー脅威の再評価
外部起点の侵害が依然として多数を占めますが、生成AIやAIノートなどを介した静かな情報集約・持ち出しといった検知しづらいインサイダー経路が可視化されています。
行動分析(UEBA)や動的リスクスコアリングを取り入れ、通常業務の違和感を早期に掬い上げる設計が重要です。
ディープフェイク詐欺の脅威
経営層を装ったビデオ会議型ディープフェイク詐欺の実害が確認されています。多要素認証の徹底と、別経路での決裁確認(コールバックや二名承認)を標準フローとして文書化してください。教育と技術対策(検知ツール、検出困難時の手続的抑止)の両輪が有効です。
リスク評価フレームワークの進化

AIを活用したERM
リスク管理(ERM)は、AIにより受動的対応から予測・予防型へシフトしています。ログや行動データを機械可読に整備し、検知・優先度付け・説明責任までを一気通貫で回すことが重要です。(この節は一般論につき、実装は自社要件に合わせてください)
動的リスクスコアリング
Microsoft Entra IDやOkta、CrowdStrikeなどの商用ソリューションでは、サインインやユーザ行動のリスクをリアルタイムに評価し、条件付きアクセス/MFAを自動付与する実装が定着しています。誤検知を抑えつつ即時対応を可能にする点で注目度が高い領域です。
確率論的リスク評価(PRA)の応用
原子力や航空で使われてきた確率論的リスク評価(PRA)をAIに適用する試みが研究・実務支援ツールの形で増えています。まだ主流実装というより“台頭中”の段階ですが、不確実性込みの因果経路を整理し、リスク説明の透明性を高めるアプローチとして注視に値します。
組織的レジリエンスと信頼構築
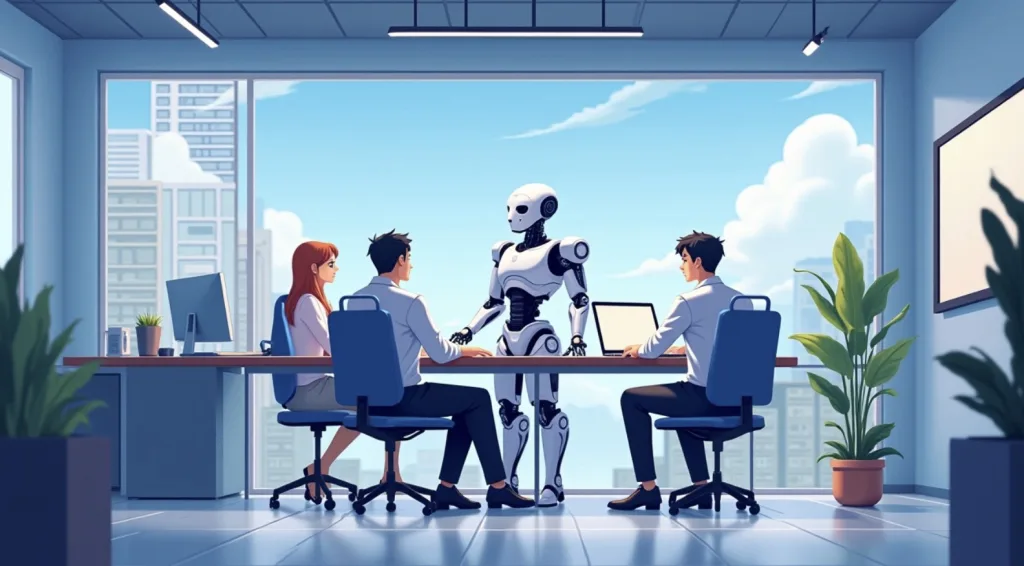
AIエージェント/アシスタントによるSOC高度化
SOCでは、生成AIアシスタントの導入が急速に進展しています。Microsoft Copilot for Security(2024年GA)に代表される調査要約・初動対応支援や、Palo Alto Networks XSIAM 3.0、Splunk AI Assistant for SPLなどのSecOps統合が拡充されています。「一般化」よりは「普及が進む」という表現が現状に即しています。
合成データとプライバシー保護
合成データは学習用データの代替として有望ですが、手法や生成過程によっては再識別のリスクが残る場合があります。匿名化の有効性検証とガバナンス(開示方針・DPIA相当の検討)をセットで設計してください。
経営層リテラシーの向上
AIリスクマネジメントの成否は、現場の努力だけでなく経営層の理解とコミットメントにかかっています。投資判断・優先順位付け・説明責任までを貫くトップ主導の体制づくりが、信頼の獲得と継続的成長に直結します。
まとめ ― 防御から信頼構築へのシフト

2025年下半期、AIリスクマネジメントの焦点は「防御」から「信頼構築」へと移りつつあります。規制準拠、サイバー防御、リスク評価、組織的レジリエンスを統合し、AIを活用しながら信頼を築くことが、企業の持続的成長に直結します。ディープフェイクからインサイダーまで多様化するリスクに備えるには、技術×人材×ガバナンスを組み合わせた総合戦略が必要です。
AIリスクを「阻害要因」ではなく競争優位の源泉に変える視点こそが、今後のAI活用を成功へ導く最大の鍵だといえるでしょう。



