「動画のアイディアはあるけれど、技術的なハードルが高い」「AIで本当に満足いく映像が作れるの?」といった疑問や不安を持つ方も多いでしょう。そんな中、Googleは誰でも簡単にAI動画を生成できる新ツール「Flow」と、さらに進化した生成AIモデルを発表しました。
本記事では、Googleの最新ツール「Flow」の特徴、今後の映像制作の可能性について詳しく解説します。
Googleが発表した新AI動画生成ツール「Flow」の正体

2025年5月、Googleは米国で開催された開発者会議「Google I/O」において、AIによる動画生成を一般向けに加速させる新ツール「Flow」を発表しました。
従来、動画生成AIは専門知識や複雑な操作が求められるものが多く、実際のクリエイターや一般ユーザーが日常的に使うにはまだ高いハードルがありました。しかし「Flow」は、誰もが直感的に扱えるシンプルなインターフェースと、強力なAIモデルによる高品質な動画生成を両立しています。
「Flow」の特徴
「Flow」の最大の特徴は、テキストプロンプト(指示文)や、いくつかの画像(“ingredients”)を組み合わせることで、8秒間のAI生成動画を簡単に作れる点です。
たとえば「海辺で夕日を見る犬」というテキストと、参考となる犬や海の画像をアップロードするだけで、AIがイメージ通りの短い動画を自動生成します。
また、生成したクリップを「シーンビルダー」機能でつなぎ合わせれば、より複雑なストーリーや映像表現も可能です。従来の動画編集ソフトに似た使い勝手をAI動画生成に持ち込んだことで、映像制作のハードルを飛躍的に下げることに成功しています。
進化した新AIモデル「Veo 3」と「Imagen 4」の革新
Flowのバックボーンとなるのが、Googleが同時に発表した新たなAIモデル「Veo 3」「Veo 2」そして画像生成AI「Imagen 4」です。これらのモデルは、従来の生成AIに比べて大幅な進化を遂げています。
とくに「Veo 3」は、ユーザーからのプロンプト(指示文)をより精密に理解し、高品質な動画と音声を同時に生成できるのが大きな特長です。映像だけでなく、背景音やキャラクターのセリフなどもAIが自動で作り出すため、よりリアルで臨場感のある動画を一括で生成できます。
また、長い指示文や複数のイベントが続くストーリーにも柔軟に対応し、これまでAI動画生成で課題とされていた「文脈の連続性」や「複雑なシーンの再現力」が大きく向上しています。
「Veo 2」では、カメラアングルのコントロールや不要なオブジェクトの除去など、より細かい編集機能が追加されました。これにより、生成された動画の仕上がりをよりクリエイターの理想に近づけることができます。
一方で、画像生成AI「Imagen 4」も進化を遂げています。画像のクオリティ向上はもちろん、従来のAI画像生成でありがちだった「文字がうまく描画できない」という課題も大きく改善され、本物のようなテキスト入り画像を生成できるようになりました。また、さまざまなファイルフォーマットにエクスポートできる柔軟性も強みです。
AI動画生成ツール「Flow」の具体的な活用イメージ

それでは実際に「Flow」を使うと、どのような映像制作が可能になるのでしょうか。Googleのデモでは、アニメーションスタイルの動画が例示されました。
たとえば、作品の冒頭でカメラがズームアウトし、動画がTVの中で再生されている様子を映し出し、さらにズームアウトして部屋全体を見せ、窓の外にカメラが抜けていってトラックが通り過ぎる――という、カメラワークやシーンの遷移を含む複雑な流れも、シーンごとにクリップを生成し「シーンビルダー」でつなげるだけでスムーズに表現できます。
こうした一連の流れは、従来であればアニメーターや映像編集者が膨大な時間をかけて制作する必要がありましたが、「Flow」ではプロンプトと画像を用意するだけで数分で完成します。映像クリエイターがストーリーボードや映像イメージを素早く「形」にするための強力なツールであると同時に、専門知識がない一般ユーザーでも手軽にイメージ動画を作れるという点が最大の魅力です。
もちろん、現時点では生成できる動画は8秒程度の短いものに限られ、映画のような長編や複雑なリアルタイム編集にはまだ課題が残ります。しかし、動画制作の最初のアイディア出しや、プロトタイピング、SNS用の短尺映像など、多様な用途で活用が広がる可能性を十分に秘めています。
GoogleのAIサブスクリプション戦略と今後の展開
「Flow」や新AIモデルの利用には、Googleが新たに開始したAIサブスクリプション「Google AI Pro」「Google AI Ultra」への加入が必要です。「Google AI Pro」ではFlowの主要機能と月100回までの動画生成が可能。「Google AI Ultra」ではより多くの生成回数やVeo 3の最新機能(ネイティブ音声生成など)への早期アクセスが提供されます。
AIによる映像表現の変革と課題
AIによる動画生成の進化は、映像制作の効率化や表現の多様化だけでなく、社会やクリエイティブ業界全体にも大きなインパクトをもたらします。今後、個人クリエイターが少人数で高品質な動画プロジェクトを実現したり、企業がマーケティングやプロモーション映像を迅速に制作したりするなど、活用の幅は飛躍的に広がるでしょう。
一方で、AI動画生成にはまだいくつかの課題も残っています。たとえば、生成された動画のクオリティや違和感、著作権や倫理的な問題、フェイク動画の拡散リスクなどです。GoogleはAI倫理や透明性の確保を重視しており、Flowや新AIモデルにもユーザーによる制御やフィードバックの仕組みを導入していますが、今後さらに社会的な議論や技術的対策が求められる場面も増えてくるでしょう。
また、AIが映像制作の現場に普及することで、従来の映像クリエイターの役割や仕事のあり方が変わる可能性もあります。人間ならではの独創性やディレクション、細やかな表現は依然として重要であり、AIツールはそれらを補完し、より創造的な作業に集中できるよう支援する存在として位置づけられることが理想です。
Googleの新AI動画生成ツール「Flow」:まとめ
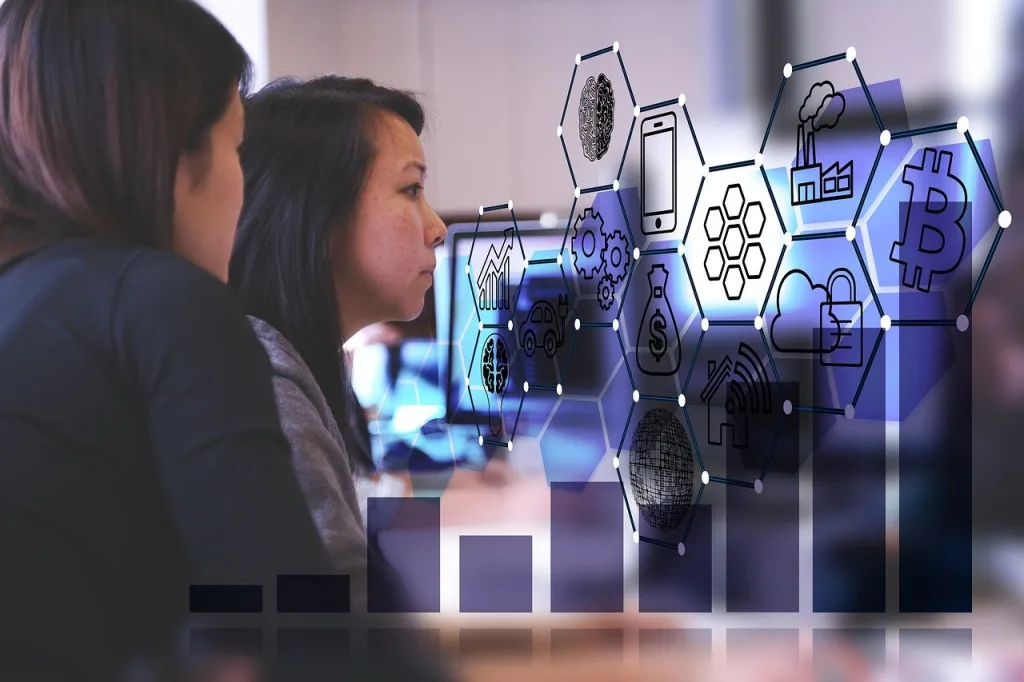
Googleの新AI動画生成ツール「Flow」と進化したAIモデルの登場は、映像制作の未来を大きく切り拓くものです。技術の進化は、クリエイターや企業だけでなく、誰もが自分のアイディアを手軽に「動画」という形で発信できる時代をもたらします。
今後もAIによる表現の幅は広がり続けるでしょう。AIと人間の創造性が融合する新しい映像表現の世界を、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。



