OpenAIは、ChatGPTの利用体験を年齢に応じて最適化するために、年齢推定と年齢認証の仕組みを段階的に整備しています。まず大きいのは、18歳未満と見なされる利用者には年齢相応の保護設定を自動適用し、疑いがある場合も安全側に倒す方針を明文化した点です。
一方で、成人向け表現をより広く扱えるようにする動きは、当初の報道では2025年12月開始が語られていましたが、その後は2026年1から3月の提供見込みとして伝えられています。現在では、年齢関連の仕組みは導入が進んでいるものの、成人向け機能の本格提供は段階導入中または提供前という整理が安全です。
この変化は一般向けの話に見えますが、企業の業務利用にも直結します。これからの社内AIポリシーは、入力してはいけない情報の管理だけでは足りず、誰がどの体験で使うかという利用者ガバナンスが重要になります。なおこの記事は2026年1月現在の情報を元に書かれています。
OpenAIが進める年齢認証──成人向けコンテンツ解禁と未成年保護の二軸戦略

1 18歳未満の保護を強化する
OpenAIは、18歳未満と識別した場合は年齢相応のポリシーを適用し、露骨な性的表現などをブロックする方針を示しています。また年齢が確信できない場合も、18歳未満向け体験を優先する考え方を明確にしています。
2 成人の体験を必要に応じて解除できるようにする
年齢推定の結果、保護設定がかかった場合でも、18歳以上であれば年齢認証を行うことで保護設定を解除できると案内されています。地域によっては、求められた場合に一定期間内の認証が必要になるケースもあります。
年齢制限付きAIが意味するもの

これまでの生成AIは、原則として同一の安全基準で広い層に提供されてきました。しかし、AIの出力が社会的影響を持つほど、年齢や立場に応じた線引きが求められます。OpenAIが年齢推定を軸に体験を分けるのは、単なる制限ではなく、安全と自由度を両立させるための設計変更です。
成人向け機能については、2026年1から3月に提供される見込みと報じられており、年齢推定精度の向上が前提条件になっています。企業側は、ベンダーの仕様変更が利用体験とガバナンスに影響する時代に入ったと捉える必要があります。
多様な利用者属性に応じた最適化の時代へ
OpenAIの取り組みは、年齢という単一属性から始まっていますが、企業内ではより多面的な属性管理が必要になります。たとえば職務内容、権限レベル、委託範囲、法的責任の範囲などです。年齢認証の話は入口であり、利用者属性に応じて使えるモデルや機能、参照できるデータ範囲を切り分ける設計思想へつながります。
なおOpenAIの利用条件として、最低年齢は13歳以上で、18歳未満は保護者の許可が必要とされています。この前提は教育機関や自治体、医療など未成年と接点がある組織ではとくに重要です。
AIを導入する企業が直面する3つの課題
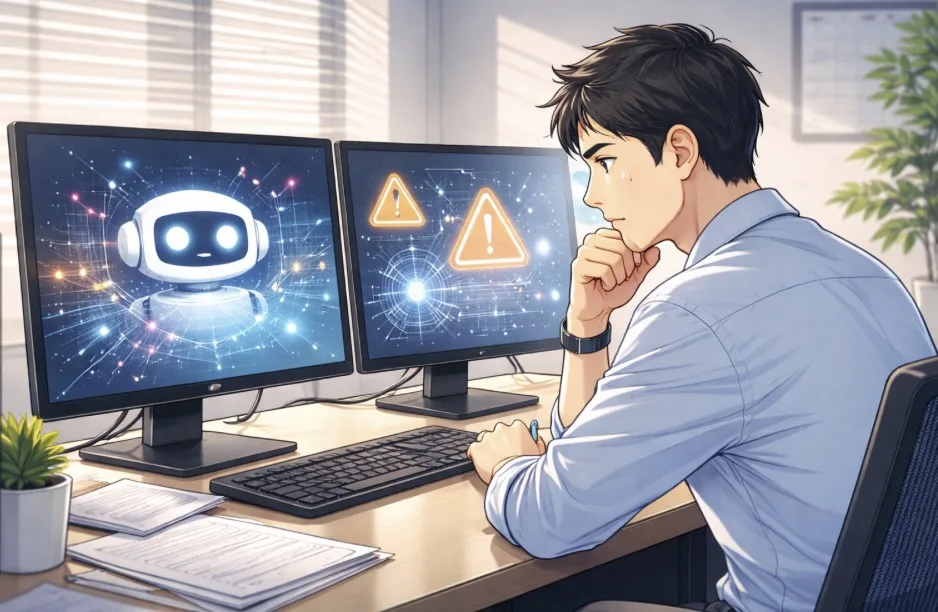
| 課題 | 内容 | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| ① 利用者属性の管理 | インターン 派遣 業務委託 取引先常駐など、属性が混在すると適用すべき体験や権限がぶれやすい | SSO連携で本人性を担保し、属性タグで権限を付与する。年齢に限らず役割ベースで制御する |
| ② 生成物の監査責任 | 体験の違いにより出力の幅が変わり、想定外の表現が監査対象になる可能性 | 出力のリスク分類と監査フローを設計し、重要領域は人のレビューを必須にする |
| ③ AIポリシーの不整合 | ベンダー側の仕様が段階導入で変わると、社内ルールが追いつかない | 定期レビュー体制を作り、仕様変更の影響範囲を評価して社内ルールへ反映する |
利用者ガバナンスとAIリスクマネジメント
これまでの社内AIポリシーは、機密や個人情報を入力しないことが中心になりがちでした。しかし年齢推定と年齢認証の流れが示すのは、利用者側の制御が不可欠ということです。具体的には、次のような設計が効きます。
- 使ってよい人を定義し、役割に応じて使える範囲を変える
- 年齢推定のように安全側に倒す挙動が起き得る前提で、業務停止を防ぐ代替手段を用意する
- 年齢認証が必要になる地域や条件がある前提で、利用部門向けの案内と問い合わせ導線を整える
年齢認証は入口にすぎない AI利用の成熟化へ
OpenAIの年齢関連の取り組みは、誰でも同じ体験から、責任ある利用へ移行する節目です。企業にとって重要なのは、成人向け機能の是非そのものではなく、仕様が段階導入で変わる時代に、利用者ガバナンスを運用として回せるかです。成人向け機能は2026年1から3月に提供見込みとされており、今後も更新が起きる前提で構えたほうがよいでしょう。
まとめ 今こそAIポリシーの棚卸しを始めるとき

ChatGPTの年齢推定と年齢認証の整備は、AIが誰に何を提供すべきかという設計の変化です。企業が生成AIを業務に取り入れるなら、次の3点を明確にする必要があります。
- 利用者属性に基づくアクセス権限
- 業務目的別の利用範囲
- 生成コンテンツの責任所在
年齢認証は単なる制限ではなく、安全にAIを使いこなす時代への第一歩です。仕様変更を前提に、全社で回るガバナンスを作れるかどうかが、信頼性と競争力を左右します。



