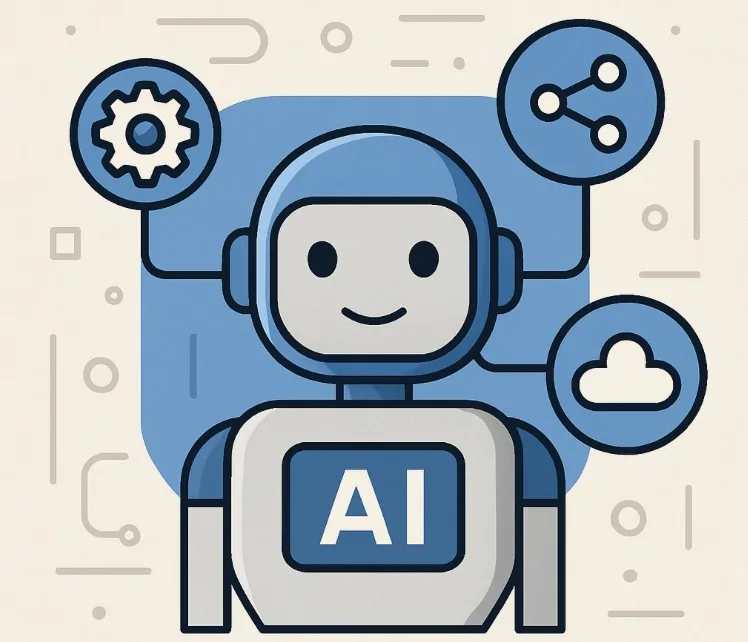生成AIの導入が進むなかで、企業の情報システム部門やIT担当者の関心は「どう使うか」から「どこで動かすか」へと移り始めています。ChatGPTやClaudeなどのクラウド型AIサービスを試した企業の多くが、次に検討するのは自社環境でAIを動かす方法です。
その際によく耳にするのが、オープンソースLLMとローカルLLMという言葉です。どちらも似た印象を与えますが、意味も役割も異なります。この記事では、オープンソースLLMとローカルLLMの違いと企業導入の観点から見た活用の方向性を整理します。
オープンソースLLMとは何か

オープンソースLLMとは、開発者や研究者がモデルの構造や学習済みの重みを公開し、誰でも利用できるようにした大規模言語モデルのことです。
代表的な例としては、Meta社のLlama 3、Mistral社のMistral 7BやMixtral、Googleが公開するGemma、AlibabaのQwen、そしてStability AIのStable LMシリーズなどがあります。これらのモデルはHugging Faceなどのプラットフォームを通じて公開されており、企業や個人が自由にダウンロードし、自分の環境で実行できます。
オープンソースLLMの魅力
オープンソースLLMの最大の魅力は、自由度と透明性です。商用モデルのようにブラックボックスではなく、モデルの中身が公開されているため、挙動を確認したり、特定の用途に合わせて再学習したりできます。また、API課金ではなく自社のサーバーで動かすことができるため、長期的にはコスト削減につながる点も大きな利点です。
一方で、導入には一定の技術力が求められます。モデルのサイズは数十億から数千億パラメータに及ぶため、GPUリソースの確保や環境構築、最適化など、エンジニアリング面での準備が必要です。さらに、商用利用にはライセンスの確認も欠かせません。Llama 3のように商用利用を認めるモデルもあれば、研究目的に限定されるモデルもあります。
ローカルLLMとは何か
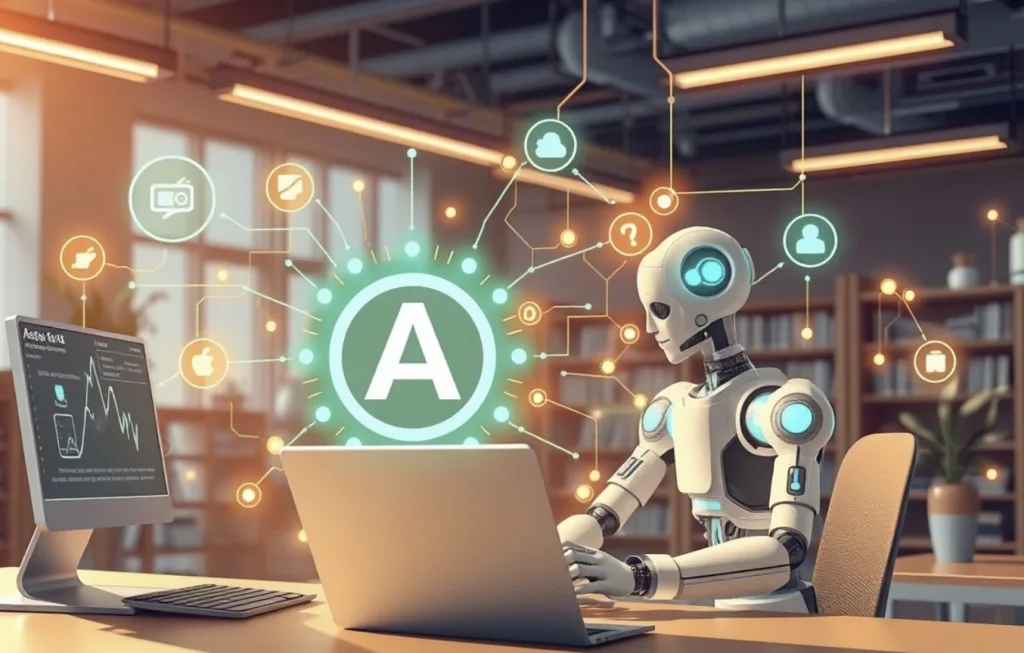
ローカルLLMとは、クラウドを介さず、企業や個人の手元環境でAIを動かすことを指します。ここでのポイントは「どのモデルを使うか」ではなく、「どこで動かすか」です。つまり、ローカルLLMは運用形態を示す概念であり、オープンソースモデルだけでなく、商用モデルをローカル実行するケースも含まれます。
たとえば、企業が社内サーバー上にLlama 3を構築して社内文書検索を行う場合、それはローカルLLMの運用です。また、最近ではノートPCや小型GPU環境でも動作する軽量モデルが増えており、Mistral 7BやPhi-3 miniなどは社内検証環境でも扱いやすいモデルとして注目されています。
ローカルLLMの魅力
ローカルLLMの最大の利点は、データを外部に出さないことです。ChatGPTのようなクラウドAIでは、入力データが外部サーバーを経由するため、社内機密や個人情報を扱う業務では利用が制限されることがあります。ローカルLLMであれば、ネットワーク内で完結するため、情報漏洩のリスクを大幅に減らせます。また、応答速度の面でもクラウド通信の遅延がなく、リアルタイム処理が求められる現場でも有利です。
一方で、運用コストやメンテナンスの負担は課題になります。モデルの更新やGPUの保守を自社で行う必要があるため、初期投資が高くなる傾向があります。しかし、長期的にはデータ保護と独自運用の両立という観点から、企業が選ぶ価値のある選択肢と言えます。
オープンソースLLMとローカルLLM:両者の違いを整理する

オープンソースLLMとローカルLLMは、対象とする概念が異なります。前者は「どのモデルを使うか」、後者は「どこで動かすか」という視点です。次の表にそれぞれの特徴をまとめます。
| 観点 | オープンソースLLM | ローカルLLM |
|---|---|---|
| 定義 | 公開されたAIモデル | 自社やローカル環境で動かすAI |
| 主な関心 | モデルの自由度・再利用性 | データ保護・運用安全性 |
| 使用例 | Llama 3、Mistral、Gemmaなど | Llama 3を社内サーバーで運用、Gemmaをローカルで実行 |
| メリット | 透明性、コスト削減、チューニング自由度 | セキュリティ、速度、社内統制との整合性 |
| デメリット | 導入難易度、技術サポート不足 | 初期コスト、保守負担 |
| 関係性 | 素材としてのAIモデル | 運用方法としてのAI環境 |
オープンソースLLMをローカル環境で運用すれば、それはローカルLLMとなります。つまり、両者は対立関係ではなく、むしろ補完的な関係にあります。
企業導入の観点から見る選択のポイント
企業が生成AIを導入する際、まず検討すべきは「どのデータを扱うか」です。顧客情報や社内ナレッジのように機密性が高いデータをAIに入力する場合、外部クラウドを介さないローカルLLMの運用が適しています。一方、外部公開データや一般的な問い合わせ対応など、情報リスクが低い領域ではクラウド型AIの方が導入しやすいでしょう。
また、AIの用途によっても選択は変わります。プロンプト生成や文書要約など、軽い処理を多く行う業務には軽量のオープンソースLLMが向いています。対して、チャットボットや社内検索のように長文や履歴を扱う場合は、より大きなモデルをローカルに構築する方が安定します。
最近では、OllamaやLM Studioのように、オープンソースLLMを簡単にローカル実行できるツールも増えています。これらを使えば、専門的な環境構築を行わずに試験導入が可能です。PoC段階ではまず小規模環境で試し、必要に応じてGPUサーバーへ移行する流れが一般的です。
まとめ:自社に合ったAIの形を見つける
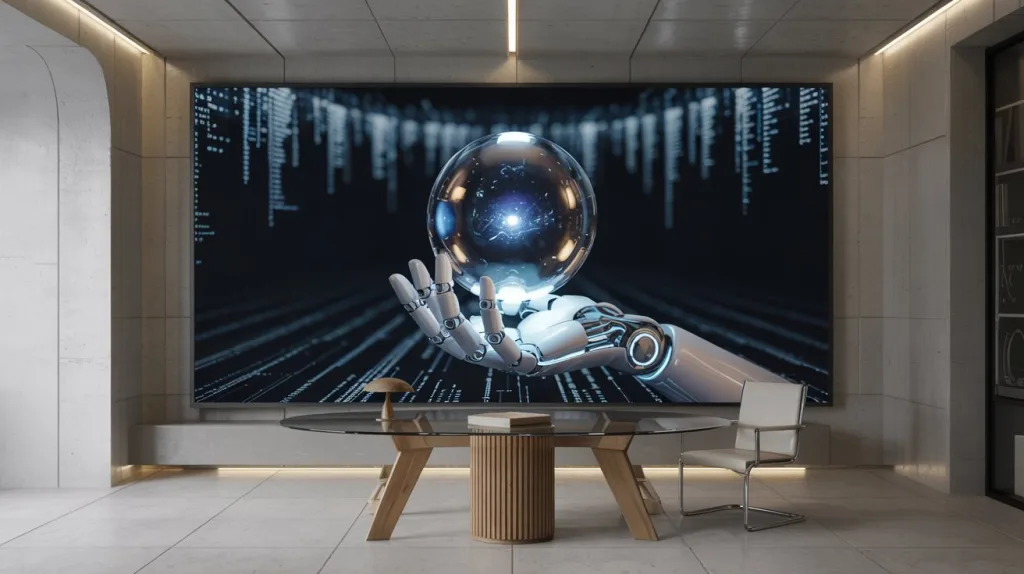
オープンソースLLMとローカルLLMは、生成AIの利用を次の段階へ進めるための重要なキーワードです。オープンソースLLMは自由で透明なAIの土台を提供し、ローカルLLMはそれを安全に運用するための器となります。どちらを選ぶかではなく、どう組み合わせて自社の価値を最大化するかが鍵です。
クラウドAIで手軽に始めるのもよいですが、社内データを活かす本格導入を見据えるなら、ローカルLLMへの移行は避けて通れません。自社のセキュリティポリシーやシステム構成を踏まえ、段階的に試すことが理想的です。生成AIはもはや外部の道具ではなく、自社の資産を学び続ける社内インフラの一部となりつつあります。今こそ、オープンソースLLMとローカルLLMの正しい理解から、次の一歩を踏み出す時期です。