生成AIの普及に伴い、多くの企業が「AI推進体制」をどう構築すべきかを検討しています。すでに専任の「AI部門」を立ち上げた企業もあれば、既存のIT部門や業務部門にその役割を担わせている企業もあります。
しかし「AI部門は必ず必要なのか」という問いに対する答えは一様ではありません。新規部門を設置するメリットとデメリット、他の推進モデルとの比較を踏まえ、自社にとっての最適解を見極めることが求められています。本記事では、AI部門の意義を整理し、企業がどのように社内の推進体制を整えるべきかを解説します。
AI部門を設置するメリット

専任のAI部門を設ける最大の強みは、全社的な司令塔として機能できる点です。企業がAI戦略を推進するうえで、意思決定と実行を一元化する部門があれば、導入から運用までをスムーズに進められます。
また、AIに関する専門人材を集約できるのも大きなメリットです。データサイエンティストやAIエンジニア、セキュリティ担当などが横断的に協力することで、知見を蓄積しやすくなります。外部ベンダーとの交渉窓口を一本化できる点も、コスト管理や契約面で有利です。
さらに、AI利用に伴うガバナンスやセキュリティルールを全社に展開する役割を担えるため、コンプライアンスリスクを抑えつつ導入を推進できるのも強みといえるでしょう。
企業内にAI部門設置する際の5つの課題

AI部門の新設は一見すると理想的な解決策に思えますが、実際にはいくつもの課題が存在します。とくに以下のポイントは、多くの企業が直面しやすい現実的な壁です。
1. 人材確保の難しさとコスト増
AI人材は市場全体で不足しており、採用競争も激化しています。専任部門を設けるには、データサイエンティストやAIエンジニア、MLOps人材、さらにはセキュリティや法務の知見を持つ人材まで必要になるケースがあります。
その結果、人件費だけでなく、研修・教育・ツール導入コストも膨らみがちです。大企業であっても投資対効果を説明するのが難しく、中堅・中小企業ではさらにハードルが高くなります。
解決方法
外部ベンダーとの協業や社内研修で既存人材を育成し、全員がAIリテラシーを持つ体制を整える。
2. 現場との温度差による“浮いた存在”化
AI部門が経営層やIT部門に近い立場で構成されると、どうしても業務部門から「現場を知らない」と見られがちです。
たとえば、現場では数秒短縮が大きな価値を持つ業務でも、AI部門が掲げる施策は抽象的・戦略的に寄りすぎてしまうことがあります。その結果、現場が協力的でなくなり、AI活用が「机上の空論」に陥る危険があります。
解決方法
現場メンバーを部門に参画させ、実際の課題を起点にプロジェクトを企画し、実効性を高める。
3. 既存部門との役割重複と摩擦
AI部門を新設すると、既存のIT部門やDX推進部門と業務範囲が重なりやすくなります。システムの導入権限をどちらが持つのか、データ管理をどちらが主導するのかといった境界が曖昧になると、部門間で摩擦が生じ、かえって推進スピードが落ちます。
さらに「予算はどちらが持つか」といった調整も複雑化し、社内政治的な課題に発展することがあります。
解決方法
責任範囲を明確化し、IT部門は基盤管理、AI部門は利活用推進と役割分担を徹底する。

4. サイロ化による全社浸透の停滞
専任部門を作ると、AIの知見や実践がその部門に閉じてしまう恐れがあります。全社的に浸透させるどころか、むしろ「AIは専門部署の仕事」という意識を生み、一般社員のリテラシー向上が進まないケースも少なくありません。
結果として、AI活用が一部のプロジェクトにとどまり、全社的な成果につながらないという矛盾が起きます。
解決方法
ナレッジ共有会や勉強会を定期開催し、全社員が学べる仕組みをつくり社内全体へ展開する。
5. 成果が見えるまでに時間がかかる
AI部門を立ち上げても、実際に目に見える成果が出るまでには一定の時間が必要です。新しい部門は人材集めや体制整備から始まり、PoCや小規模導入を経て全社展開に至ります。
その過程で経営層から「投資に対して成果が出ていない」と指摘され、存続意義が問われるリスクもあります。スピード感を重視するAI活用の文脈では、このタイムラグが大きな課題になり得ます。
解決方法
小規模PoCで早期に成果を示し、段階的にスケールアップすることで経営層の理解を得る。
他の推進モデルとの比較

IT部門主導型
既存のIT部門にAI推進を担わせるモデルです。システム運用やセキュリティ体制を活かせるため、信頼性の高い基盤構築が可能です。ただし、業務部門のニーズに即した施策を打ち出すには限界があり、現場との距離が課題になることがあります。
業務部門主導型
業務部門が自らAI導入をリードするケースです。現場の課題を直接解決できるため、PoCや小規模導入には適しています。しかし、全社的な統制やセキュリティルールの策定が弱くなりがちで、スケール展開には不向きです。
ハイブリッド型(AI CoE:センター・オブ・エクセレンス)
近年注目されているのが、IT部門・業務部門・経営層をつなぐ横断組織である「AI CoE」です。各部門から人材を集めて小規模チームを作り、社内のベストプラクティスを横展開する仕組みです。このモデルは、全社的なガバナンスと現場ニーズの両立を図れる点で、多くの企業から「最適解のひとつ」として採用が進んでいます。
推進体制の最適解をどう考えるか
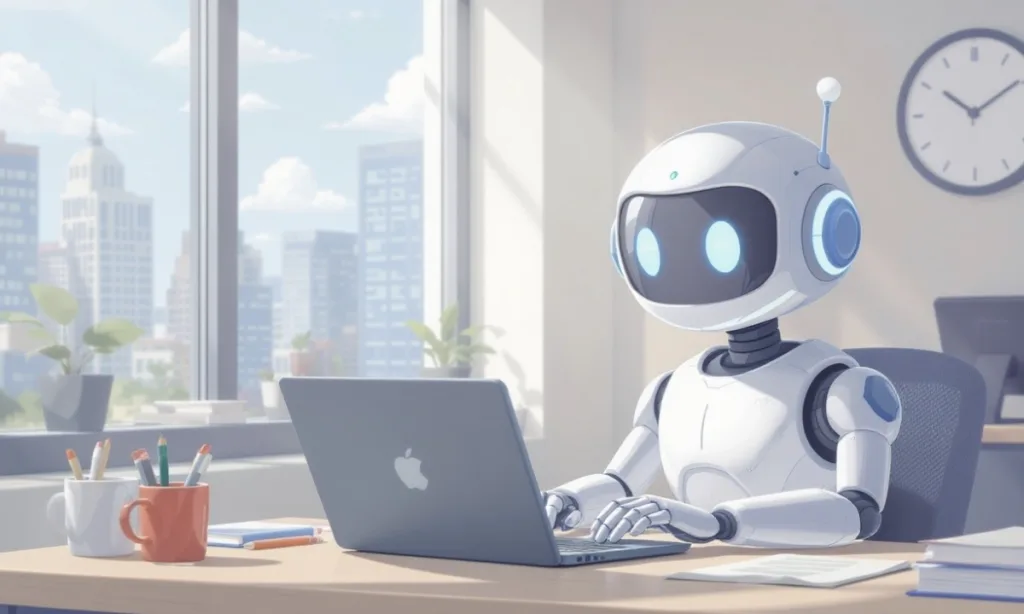
AI部門を設けるかどうかは、自社の規模や業種、導入目的によって異なります。大企業で全社横断的なプロジェクトを推進する場合は、AI部門やCoEの設立が有効でしょう。一方で、中堅・中小企業では新設部門を持つほどのリソースがなく、既存のIT部門や業務部門の協力体制で十分に対応できるケースも多いです。
重要なのは「AIをどう活用するか」というビジョンを先に明確に描くことです。目的が曖昧なまま部門だけを設立すると、コストや混乱を生む可能性があります。むしろ、最初は小さなプロジェクト単位で実績を積み、その後に組織的な体制を整える段階的なアプローチが有効です。
導入ステップと実践ポイント

- 社内ニーズとリスクを洗い出す
どの部門でAIが有効か、どのようなリスクがあるかを整理することから始めます。 - 現有リソースで担える範囲を見極める
IT部門やDX推進チームにどこまで任せられるかを確認し、追加が必要な人材やスキルを特定します。 - 必要に応じてAI担当者を配置し、徐々にチーム化
いきなり部門を新設せず、まずは専任担当者を置く形から始め、必要に応じて拡大するのが現実的です。 - 全社浸透を前提としたルール策定と教育を進める
セキュリティ・利用ルール・プロンプト設計のトレーニングなどを並行して実施することで、現場での定着を促進できます。
“AI部門”は本当に必要?:まとめ

AI部門を新設することは、必ずしも全企業にとっての最適解ではありません。大切なのは、AI活用を全社にどう根付かせ、成果につなげるかという視点です。AI部門はそのための一つの選択肢であり、IT部門主導型や業務部門主導型、あるいはAI CoEのような横断型組織も有効なアプローチです。
自社の規模や文化に合わせて推進体制を設計し、「部門ありき」ではなく「活用のビジョンありき」で考えることが、生成AI時代を乗り切る鍵となるでしょう。



