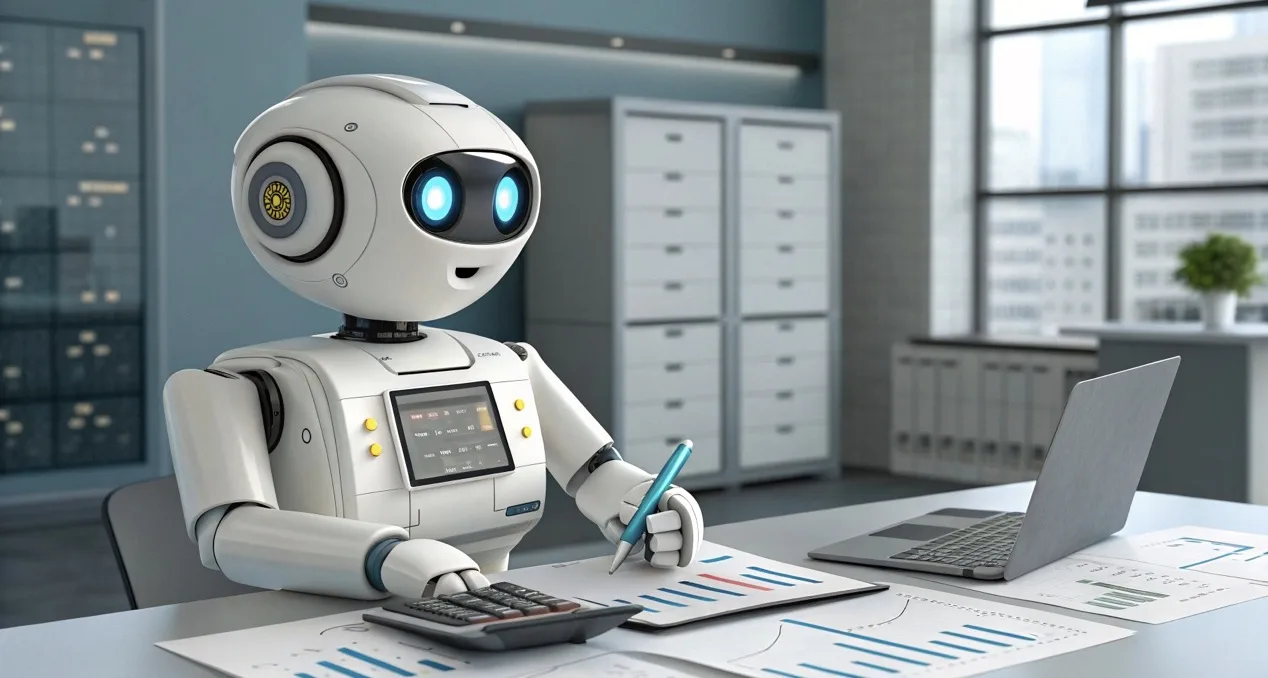「300字ぴったりで」「箇条書きで」「〜ですます調で」——これらの細かい指示は、かつてGPT-4o時代には必須の作法でした。しかし、GPT-5の登場により、そのようなプロンプトでの制約はむしろAIの能力を制限してしまう可能性があります。
GPT-5では推論力と自律的な補完能力が飛躍的に向上し、プロンプト設計の常識が根本から変わりました。本記事では、「もう必要なくなった従来のテクニック」と「新時代で真価を発揮する設計アプローチ」を体系的に整理し、ビジネス現場での成果を最大化するための実践的なプロンプト設計ノウハウをお届けします。
GPT-5時代のプロンプト設計のコツ①:不要になったこととは?

1-1.厳格すぎる文字数や語尾の指定
GPT-4oでは「300字ぴったり」「〜ですます調で統一」と細かく縛らないと安定しませんでした。しかしGPT-5では文脈理解が向上し、緩やかな指定でも自然に整った出力を返します。過度な制約は逆に情報を削いでしまうため、必要最小限にとどめるのが賢明です。
1-2.役割指示の羅列
「You are a professional writer」「You are an IT consultant」などを並べて強調する手法は、GPT-4oでは有効でした。GPT-5では一度の設定で十分に役割を理解し、指示を補完できます。冗長な役割付与は不要になりました。
1-3.出力フォーマットの過度な固定
表形式やステップ形式を厳格に指定するよりも、GPT-5では「表にまとめて」程度の方向づけで十分です。細かいネストや複雑な形式指定は、かえって回答の柔軟性を損ねます。
1-4.手順を強制的に分割する指示
「Step1〜10で回答せよ」と逐次的に縛る必要はなくなりました。GPT-5は自律的に最適な流れを構築できるため、段階的に情報を追加していくマルチターン対話の方が効果的です。
GPT-5時代のプロンプト設計のコツ②:新たに意識すべきこと

GPT-5は推論力・文脈理解力が格段に高まったことで、従来のような「細かく縛る」スタイルではなく、方向性を示すプロンプト設計が成果を左右します。ここでは実務に直結する観点ごとに、有効なプロンプト例を紹介します。
2-1. 目的・読者・利用シーンを明示する
GPT-5は「誰に」「何のために」という情報を与えると、自然に出力のトーンや重点を調整してくれます。
有効プロンプト例
- ✗ 悪い例:「この会議を要約して」
- ○ 良い例:「経営層が5分で把握できるように、会議の要点を3つに絞って要約して。数字や事例があれば必ず含めて」
2-2. 評価基準や前提を共有する
単に「提案して」ではなく、何を基準に良し悪しを判断するかを伝えると、GPT-5は自己最適化して出力します。
有効プロンプト例
- ✗ 悪い例:「生成AI導入の提案をまとめて」
- ○ 良い例:「生成AI導入の提案をまとめて。評価基準は①コスト削減効果②セキュリティ③社内教育のしやすさ。各項目ごとに5点満点で自己採点して」
2-3. 自己評価や改善の仕組みを組み込む
GPT-5は「案を出すだけ」でなく、自分で比較検討し改善するのが得意です。
有効プロンプト例
- ✗ 悪い例:「AI導入のキャッチコピーを考えて」
- ○ 良い例:「AI導入のキャッチコピーを3案考えて。それぞれの強みと弱みを説明したうえで、最も効果的な1案を改稿して」

2-4. 不確実性と根拠の扱いを指示する
推論力が高い分、GPT-5は仮説的な答えを出すこともあります。そこで「根拠提示」や「推測の明示」を求めると信頼性が増します。
有効プロンプト例
- ✗ 悪い例:「AI導入に失敗した事例を教えて」
- ○ 良い例:「AI導入に失敗した事例を3つ紹介して。根拠となる公開情報がある場合は引用を添えて。もし推測が含まれる場合は“推測”と明記して」
2-5. マルチターン前提で設計する
GPT-5は一度にすべてを出させるよりも、段階的に深める方が高品質です。ドラフトから確認・改善の流れを前提にするのが有効です。
有効プロンプト例
- 1回目:「次のテーマで記事の骨子を作って」
- 2回目:「その骨子をもとに、導入部を300字で書いて」
- 3回目:「導入部の文体を経営層向けにリライトして」
2-6. 組織でのテンプレート化
プロンプトの属人化を防ぐため、業務ごとに「標準プロンプト」を用意すると効果的です。GPT-5は短いテンプレでも意図を深く理解します。
テンプレ例:会議要約
「この議事録を要約してください。対象読者は経営層。重要な決定事項・課題・次のアクションを3項目に整理し、箇条書きで示してください」
テンプレ例:FAQ生成
「顧客からの問い合わせ履歴を参考に、FAQを3問作成してください。回答はわかりやすく、顧客に安心感を与えるトーンで」
テンプレ例:レポート作成
「マーケティング施策の結果をまとめてください。管理職向けに、数字は表で整理し、要点は200字以内で解説してください」
GPT-5では「細かい縛り」ではなく「文脈の共有」を!
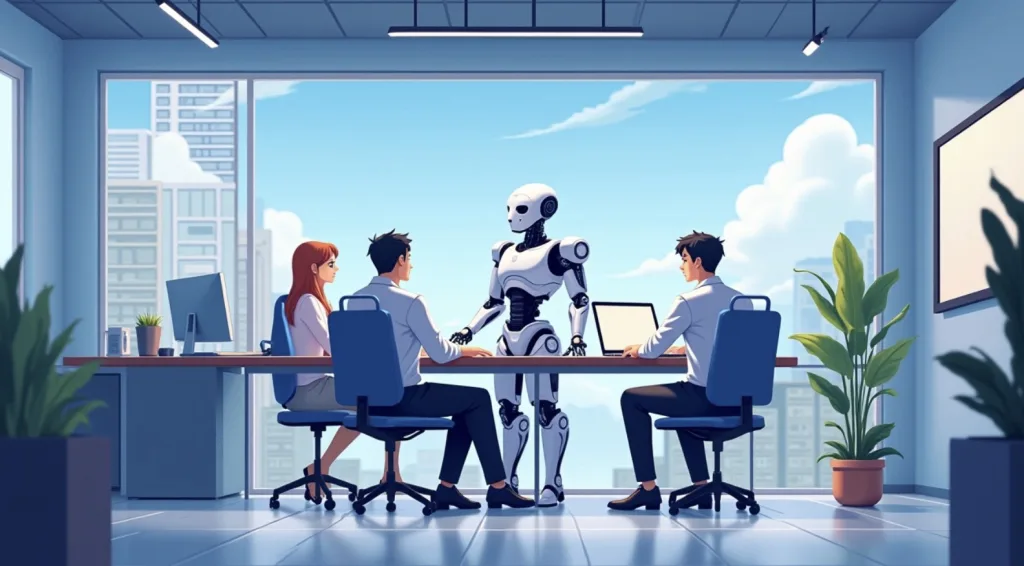
GPT-5時代に意識すべきは、「細かい縛り」ではなく「文脈の共有」です。
- 目的・読者像・利用シーンを伝える
- 評価基準や前提条件を提示する
- 自己評価や改善を組み込む
- 不確実性の扱いを明示する
- マルチターンで深める
- テンプレートで全社共有する
この意識転換によって、GPT-5を業務現場で最大限に活用できます。
具体例
- 要約依頼
Before:「300字以内で要約。ですます調。箇条書きで」
After:「経営層が5分で理解できるように、主要な3点に絞って要約して」 - FAQ作成
Before:「質問と回答を3つ、表形式で出力」
After:「顧客サポート担当がそのまま使える形で、質問と回答を3つ作成。顧客に安心感を与えるトーンで」 - レポート作成
Before:「表形式で詳細をすべて記載」
After:「管理職向けに、数字は表にまとめ、解釈部分は簡潔な文章で補足する」
GPT-5時代のプロンプトのコツ:まとめ

GPT-5の登場によって、プロンプト設計は「細部を縛る技術」から「文脈と目的を共有する設計思考」へとシフトしました。不要になったのは冗長な役割指定や厳格すぎる形式縛りであり、新たに重要になったのは利用目的・読者像・評価基準の明示です。
つまり、プロンプトは単なる入力文ではなく、AIに対して“なぜ・誰のために・どう評価するか”を伝える指示書です。これを意識することで、GPT-5を最大限に活用し、企業の業務効率化や成果創出に直結させることができるでしょう。