「検索」か「実行」か?企業AI市場を二分する1兆円企業
「AIを全社導入したいが、何から始めればいいのか」——多くの経営者やIT部門が直面するこの悩みに、実は明確な答えが出始めています。企業AI市場では今、評価額1兆円のシリコンバレー企業と、年商11億円ながら前年比6倍成長を遂げるパリのベンチャーという、対照的な2つのプレイヤーが台頭しています。驚くべきことに、後者は前者の2.5倍もの資本効率で成長しているのです。
この記事では、GleanとDust AIという2社の戦略的差異を読み解くことで、あなたの会社がAI導入で「トップダウン」と「ボトムアップ」のどちらを選ぶべきか、その判断軸が見えてきます。
エンタープライズAI市場に現れた「二極化」という新潮流

企業向けAI市場は現在、興味深い二極化を見せています。一方の極には「知識のインフラ」を構築するアプローチがあり、もう一方には「実行の自動化」に特化するアプローチがあります。
前者の代表格が、2025年時点で企業評価額72億ドル(約1兆円)、年間経常収益1億ドル超を達成したGleanです。同社は総額7.6億ドル超という巨額の資金を調達し、Sequoia CapitalやDST Globalといった著名投資家の支援を受けています。
対照的に、後者を代表するのがフランス・パリ発のDust AIです。総調達額はわずか2,150万ドルながら、年間経常収益730万ドルを達成し、前年比6倍以上という驚異的な成長率を記録しています。注目すべきは、Dustの従業員1人あたりの収益が11万ドル(約1,650万円)を超えるという、アーリーステージ企業としては極めて高い生産性です。調達額に対する収益の比率で見ると、Dustの資本効率はGleanの2.5倍以上に達しています。
この対比が示しているのは、単なる企業規模の違いではありません。エンタープライズAIを導入する際の、根本的に異なる2つの哲学の存在です。あなたの会社がAI導入で成功するためには、この哲学的な違いを理解することが不可欠です。
Gleanの戦略:「知識のOS」として君臨する野望
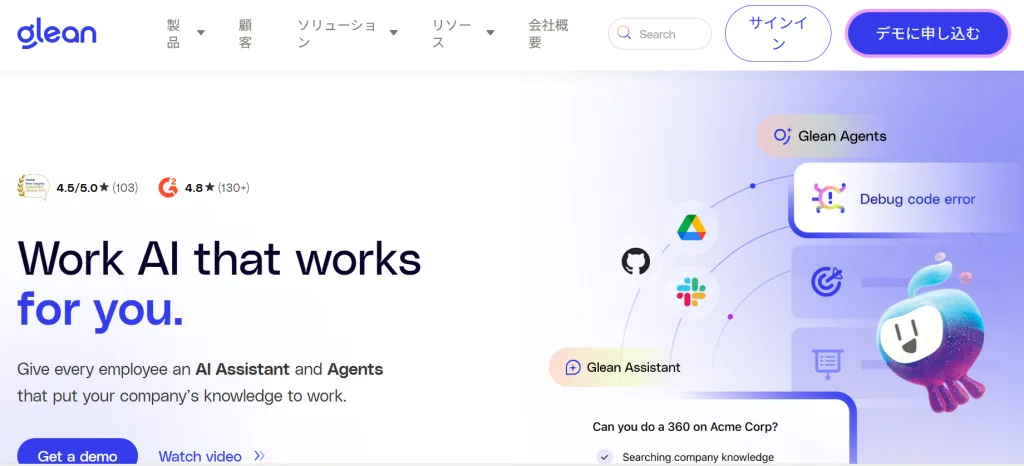
Gleanのアプローチは、一言で表現すれば「企業知識のOS化」です。同社は2019年の創業時、「AI駆動の企業検索エンジン」として出発しましたが、現在では包括的な「Work AI」プラットフォームへと進化を遂げています。その核心にあるのが「Enterprise Knowledge Graph」という独自技術です。
このナレッジグラフは、単なるキーワード検索のインデックスではありません。企業内に散在するデータ、それを利用する人材、そしてそれらが関わるプロセス間の複雑な関係性を深く理解します。100以上のSaaSアプリケーション、Salesforce、Google Drive、Atlassian、Slackなどからデータを吸収し、各ユーザーの役割や業務、チームメイトとの関係性といった文脈に基づいて、高度にパーソナライズされた回答を生成できます。
Gleanの真の強みはセキュリティアーキテクチャ
Gleanの真の強みは、この知識基盤の上に構築された「Glean Protect」というセキュリティアーキテクチャにあります。大企業がAIの全社導入を躊躇する最大の理由は、セキュリティとコンプライアンスのリスクです。
Gleanは製品設計の初日からセキュリティを最優先事項として組み込んでおり、ソースアプリケーション側で設定された既存の権限を100%厳格に継承します。さらに、SOC 2 Type II、ISO 27001、GDPR、HIPAAといった厳格なコンプライアンス基準に準拠しています。
実際、Booking.comは1万4,000人の従業員にGleanを全社導入し、プロモーションビデオのスクリプト作成プロセスを8週間から2週間に短縮しました。Deutsche Telekomは「AskT」という従業員コンシェルジュを構築し、社内情報の検索時間を平均2分以上からわずか18秒へと劇的に短縮しています。これらの事例が示すのは、Gleanが単なる「検索ツール」ではなく、グローバル企業の「コアインフラ」として機能しているという事実です。
Gleanの公式サイトはこちら
Dust AIの戦略:「現場のROI」で勝負する実行特化型
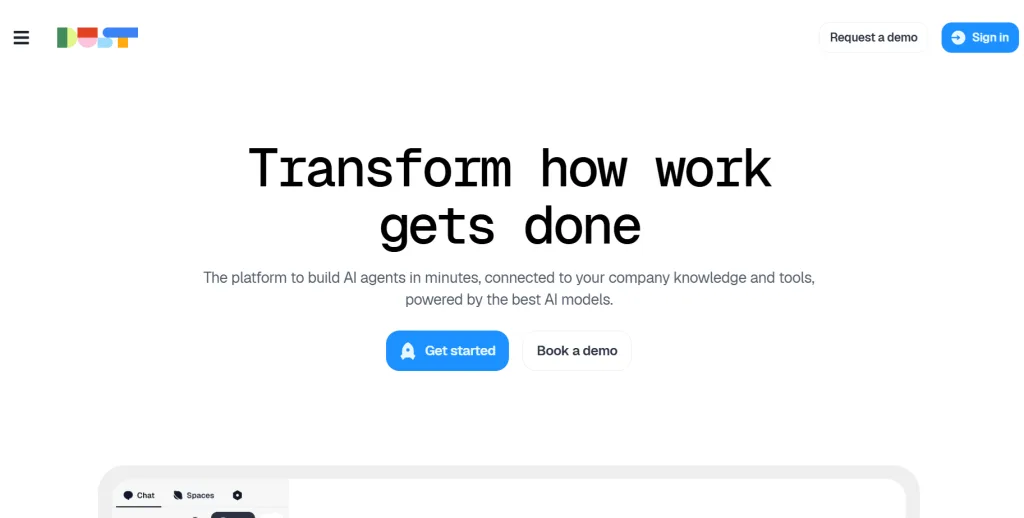
Gleanが「知識のシステム・オブ・レコード」を目指すのに対し、Dust AIは「実行のオーケストレーション」に特化しています。同社の核心にある思想は「検索ではなく実行」です。Dustが定義する「実行」とは、単に質問に答えるチャットボットを超え、AIエージェントが実際に作業を完了することを指します。
Dustの技術的な特徴は、重厚なインフラを自社で構築しない「軽量アーキテクチャ」にあります。同社は「モデル・アグノスティック」なアプローチを採用し、OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistralなど、市場に存在する最先端のモデルから、タスクに応じて最適なものを自由に選択・切り替えできます。実行の信頼性は、ワークフロー・オーケストレーション・プラットフォーム「Temporal」の採用によって担保されており、1日に1,000万件を超えるアクティビティを処理しています。
Dustの真の強みは「導入率」
この「インフラを持たない」戦略こそが、Dustの高い資本効率の秘密です。Gleanが7.6億ドル超の資金を投じて知識グラフという重厚なインフラを自社で構築・運用しているのとは対照的に、Dustは「LLM」と「オーケストレーション」という複雑なコンポーネントを外部のベスト・オブ・ブリードなPaaSに依存し、自社のリソースを「企業のコンテキストとツールを接続するレイヤー」という最も付加価値の高い部分に集中させています。
Dustの真の強みは、驚異的な「導入率」にあります。コンサルティングファームのCMI Strategiesでは95%というAI導入率を達成し、Personaでは80%、Patchでは70%がAIエージェントを毎週利用しています。
特に注目すべきは、B2B SaaS企業Clayの事例です。GTMエンジニアリングチームの20名において、Dustの導入率は100%に達し、毎月約58時間の時間節約を実現しました。これは「丸一週間の労働時間以上に相当」する明確なROIです。
Dustの公式サイトはこちら
「トップダウン」か「ボトムアップ」か:導入アプローチの本質的な違い

GleanとDustの対立が浮き彫りにするのは、AI導入における二つの異なる哲学です。Gleanは、CIOやCISOといった経営層のトップダウンの承認を得て、全社インフラとして導入されます。
その評価額に対する72倍という異常に高い株価売上高倍率は、投資家がGleanを単なる「検索ツール」ではなく、「次世代のエンタープライズOS」として、将来的にSalesforceやMicrosoftに比肩する存在になると期待していることを示しています。
一方、Dustは現場の部門長が、特定の業務課題を解決するための即時のROIを武器に採用されます。Gleanのような全社的なセキュリティレビューを待たずに、部門単位で迅速に価値を証明できるのがDustの「軽量かつ俊敏」なGTM戦略の本質です。
66名という少数精鋭のチームで、エンタープライズ・グレードの実行プラットフォームを迅速に市場投入できるのは、このプロダクトレッド・グロース(PLG)モデルの賜物です。
本当の競合はCopilot
興味深いのは両社にとっての最大の競合が、実は互いではなくMicrosoft Copilotだという点です。しかし、GleanとDustは、Copilotが作り出す「AIの空白地帯」を巧みに埋めることで共存・成長しています。
Gleanは「水平的特化」戦略として、Copilotがアクセスできない非Microsoftデータを統合し、企業知識の真の全体像を提供します。Dustは「垂直的特化」戦略として、Copilotでは不可能な特定のワークフロー実行を自動化します。
エンタープライズAI市場の未来:融合という必然
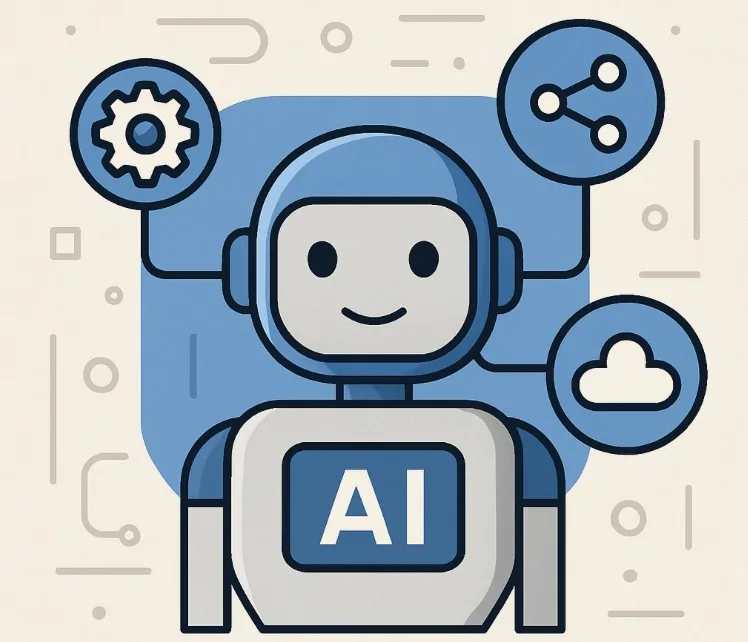
エンタープライズAI検索市場は、2022年の50億ドルから2032年には122億ドルへと、年平均成長率9.6%で成長すると予測されています。この成長市場において、GleanとDustが争う未来には3つのシナリオが考えられます。
二極的共存と最終的な融合
最も蓋然性が高いのは「二極的共存と最終的な融合」というシナリオです。短期的には、企業はIT部門主導でGleanを「全社的な知識インフラ」として導入し、同時に現場部門主導でDustを「部門特化の実行エージェント」として導入する「両方買い」の状況が発生するでしょう。
しかし、長期的には両者は競合ではなく「補完関係」になります。Dustの実行エージェントが真に複雑なタスクを自律実行するためには、Gleanが提供するような、全社100以上のSaaSにまたがり、かつ厳格な権限管理がなされた「信頼できる知識源」が不可欠です。
GleanはエンタープライズAIにおける究極の「バックエンド(Knowledge API)」としての地位を確立し、DustはGleanの安全なKnowledge APIを消費し、複雑なワークフローをオーケストレーションする最も強力な「フロントエンド(Action Orchestrator)」として進化するでしょう。
急成長する2つのエンタープライズAI企業から学ぶ導入戦略:まとめ

あなたの会社がAI導入で成功するためには、この「知識」と「実行」という2つのレイヤーの違いを理解し、自社の成熟度とニーズに応じた戦略を選択することが重要です。全社的なデータガバナンスとセキュリティが最優先なら、Gleanのようなトップダウン型のアプローチが適しています。
一方、特定部門での迅速なROI実証が必要なら、Dustのようなボトムアップ型のアプローチが有効でしょう。そして最終的には、両方のレイヤーを統合することが、エンタープライズAIの真の価値を引き出す鍵となるのです。



