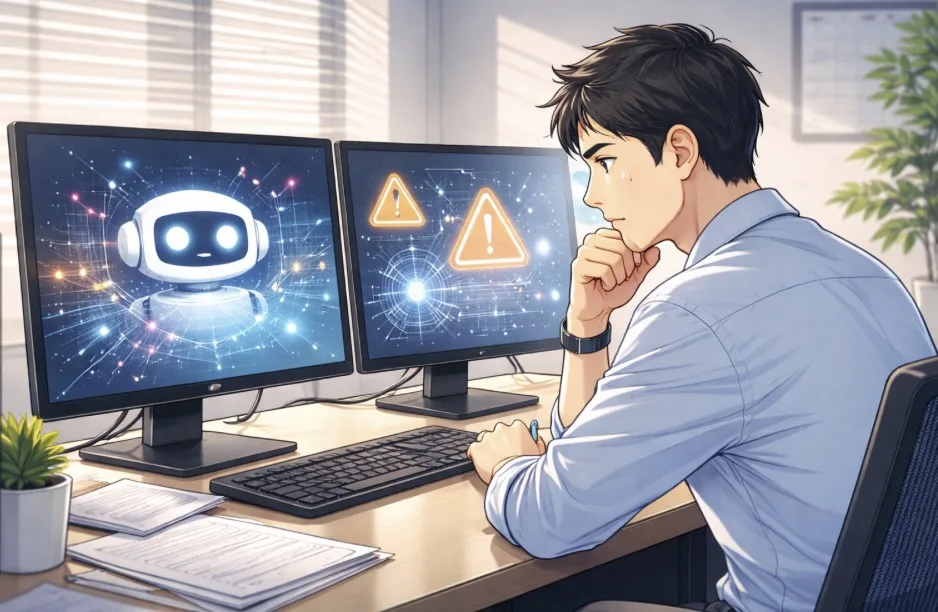生成AIは、調査、資料作成、要約、アイデア出しなど、企業の業務効率を大きく向上させる存在として急速に普及しています。一方で、もっともらしい誤情報を事実のように生成してしまうハルシネーションが、企業利用における新たなリスクとして顕在化しています。
本記事では、生成AIのハルシネーションはなぜ防げないのかという前提から出発し、企業利用で起きやすい事故の構造と、情シスが取るべき現実的な対策を整理します。生成AIを安全に活用し続けるために、今あらためて考えるべきポイントを解説します。
第1章 生成AIのハルシネーションとは何か

1-1 ハルシネーションの基本的な意味
生成AIのハルシネーションとは事実ではない情報を、あたかも正しいかのように出力してしまう現象を指します。存在しない制度や法律、架空の数値、実在しない文献や参考資料を、自然な文章で提示するケースが典型例です。
重要なのは、これは単なる誤変換や入力ミスではないという点です。生成AIは文章を破綻なく構成する能力が高いため、内容に誤りが含まれていても、読み手が違和感を覚えにくいという特徴があります。とくに業務文書やレポートの形になると、確認せずに使ってしまうリスクが高まります。
1-2 なぜ人はハルシネーションに騙されやすいのか
ハルシネーションが問題になりやすい理由の一つは、生成AIの出力が断定的であることです。曖昧な表現ではなく、結論を言い切る形で文章が作られるため、人は無意識のうちに正しい情報だと受け取ってしまいます。
また、箇条書きや論理的な構成、専門用語を交えた説明など、人が信頼しやすい形式で出力される点も見逃せません。出典が明示されているように見える場合でも、実際には存在しない文献名やURLが含まれていることがあります。忙しい業務の中では、一つひとつ裏取りをする時間が取れず、そのまま利用されてしまうケースも少なくありません。
このように、ハルシネーションは技術的な問題であると同時に、人間側の判断プロセスとも密接に関係しています。企業利用においては、個人の注意力に頼るだけでは限界があり、組織としてどう扱うかを考える必要があります。
第2章 なぜハルシネーションは防げないのか

2-1 生成AIの仕組み上の限界
生成AIは、質問に対して正解を検索して返す仕組みではありません。大量の学習データをもとに、次に来そうな単語や文の並びを確率的に予測しながら文章を生成しています。そのため、内容が事実かどうかを判断しているわけではなく、あくまでもっともらしい文章を作ることに最適化されています。
この仕組み上、情報が存在しない場合や曖昧な質問をされた場合でも、生成AIは沈黙せず、何らかの答えを返そうとします。その結果、実在しない制度や数値、根拠のない説明が、自然な文章として出力されてしまうことがあります。これはモデルの性能が低いから起きるのではなく、生成AIという技術の前提条件に由来するものです。
2-2 モデルが高性能でも起きる理由
近年の生成AIは精度が大きく向上していますが、それでもハルシネーションが完全になくなることはありません。理由の一つは、学習データに含まれない情報や、最新の出来事、企業固有のルールや数字に対しては、正確な判断ができないためです。
とくに企業利用では、社内規程や独自の業務フロー、業界特有の事情など、外部には公開されていない情報を扱う場面が多くあります。このような内容について質問すると、生成AIは一般的な知識や推測をもとに回答を組み立てるため、事実とずれた内容が出力されやすくなります。しかも、その誤りを自信満々に提示する点が、利用者にとって厄介な部分です。
2-3 完全防止が不可能という前提
企業で生成AIを使う際に重要なのは、ハルシネーションをゼロにすることを目標にしないことです。完全防止を目指すあまり、過度な制限やチェックを重ねると、現場では使いにくくなり、結果として非公式な利用が増えてしまいます。
現実的な考え方は、ハルシネーションが起きる前提で、どこまで許容し、どこから人が責任を持って確認するのかを整理することです。生成AIは補助的なツールであり、最終判断や重要な意思決定を任せる存在ではありません。この前提を組織として共有できていないと、いつか必ず事故につながります。
第3章 企業利用で実際に起きている事故例
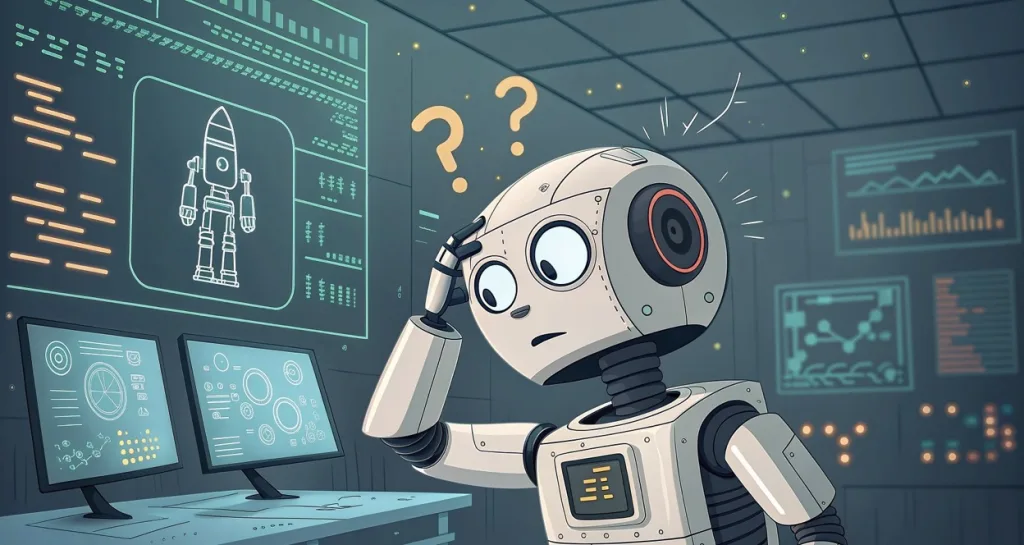
3-1 社内資料やレポートでの誤情報
企業でよく見られるのが、生成AIで作成した社内資料やレポートに、誤った情報がそのまま混入してしまうケースです。たとえば、市場規模や業界動向の数値が実在しないものだったり、存在しない制度やガイドラインがあたかも公式情報のように記載されたりすることがあります。
資料としての体裁が整っているため、作成者自身も誤りに気づかないまま、上司や関係部門へ提出してしまう例も少なくありません。確認工程が省略されがちな下書き用途ほど、ハルシネーションの影響は見えにくく、後から問題が発覚しやすい傾向があります。
3-2 意思決定や判断への影響
より深刻なのは、生成AIの出力が意思決定の材料として使われてしまうケースです。企画書や提案書、顧客向け説明資料などにハルシネーションが含まれると、誤った前提で判断が行われる可能性があります。
とくに、法令解釈や契約条件、セキュリティ要件など、正確性が求められる分野では影響が大きくなります。一度社外に出た情報は訂正が難しく、信頼低下やクレームにつながることもあります。この段階になると、単なる作業ミスではなく、企業としての管理体制が問われる問題になります。
3-3 情シスが後から気づくケース
ハルシネーションによる事故は、情シスがリアルタイムで把握できないことも多いです。現場が独自に生成AIを使い、資料作成や調査を進めた結果、外部指摘やトラブルをきっかけに初めて問題が表面化します。
この背景には、生成AIの利用実態が情シスに共有されていないことや、どの用途までAIを使ってよいのかが曖昧なまま運用されていることがあります。事故が起きてから対策を考えるのではなく、起きる前提で設計しておく必要があるという点が、この章で見えてくるポイントです。
第4章 情シスが直面する課題

4-1 正しいかどうかを誰が確認するのか
生成AIの出力に誤りが含まれていた場合、その正しさを誰が確認するのかが曖昧な企業は少なくありません。現場担当者が確認する前提になっていても、業務の忙しさや専門知識の不足から、十分な裏取りが行われないケースがあります。
一方で、情シスがすべての内容をチェックすることは現実的ではありません。生成AIの利用が広がるほど、確認対象は膨大になります。結果として、誰の責任で確認するのかが不明確なまま運用が進み、事故が起きたときに対応が後手に回る構造が生まれます。
4-2 ツールが増えすぎて把握できない
生成AIは単体のチャットツールだけでなく、業務アプリやクラウドサービスの機能として組み込まれ始めています。メール、ドキュメント、検索、分析など、日常業務の中に自然に入り込むため、利用実態を把握することが難しくなっています。
情シスとしては、どのツールに生成AIが搭載されているのか、どの部門が何に使っているのかを把握しきれない状況に直面します。その結果、リスクの高い用途と比較的安全な用途の区別がつかないまま、包括的に管理しようとして失敗することもあります。
4-3 ハルシネーションを事故として扱っていない
多くの企業では、情報漏洩やシステム障害については明確なインシデント定義と対応フローがあります。一方で、生成AIのハルシネーションによる誤情報については、事故として扱う基準が定まっていないケースが目立ちます。
誤った情報が社内外に出た場合でも、単なるミスとして処理され、根本的な対策が行われないことがあります。しかし、影響範囲や信頼へのダメージを考えると、ハルシネーションも立派な業務リスクです。情シスとしては、これを想定外の事象ではなく、管理対象のリスクとして位置づける必要があります。
第5章 企業が取るべき現実的な対策

5-1 ハルシネーション前提の利用ルール
生成AIを企業で使う際は、ハルシネーションが起きる前提で利用ルールを設計することが重要です。すべての用途で正確性を求めるのではなく、どの業務なら許容でき、どの業務では慎重な確認が必要なのかを切り分けます。
たとえば、アイデア出しや構成案の作成、文章の下書きや要約といった用途では、生成AIの活用効果が高く、多少の誤りがあっても人が修正できます。一方で、法令解釈、契約条件、数値の確定、対外的な公式文書については、生成AIの出力をそのまま使わないことを明確にする必要があります。
5-2 利用用途の切り分け
ルールを実効性のあるものにするためには、利用用途を具体的に示すことが欠かせません。抽象的な禁止事項だけでは、現場は判断に迷ってしまいます。安全性の高い用途と注意が必要な用途を分けて示すことで、現場が安心して使える範囲が明確になります。
また、重要な判断に生成AIを使う場合は、必ず人による確認を挟む前提を設けます。確認者を明確にすることで、責任の所在が曖昧になることを防げます。情シスとしては、現場と相談しながら、現実的な線引きを行うことが求められます。
5-3 技術的な補助策
ルール運用を支えるために、技術的な補助策も有効です。社内データに限定して情報を参照させる仕組みを使えば、外部の不確かな情報をもとにしたハルシネーションを減らせます。出典を明示させる、引用ルールを設けるといった工夫も、確認作業の負担軽減につながります。
ただし、技術的対策だけでハルシネーションを完全に防げるわけではありません。あくまで人の判断を補助する仕組みとして位置づけ、過信しない運用が重要です。
5-4 事故が起きたときの対応
ハルシネーションによる誤情報が発見された場合に備え、対応フローを事前に整えておく必要があります。社内での修正や周知だけで済むのか、外部への説明や訂正が必要なのかを判断する基準を決めておくことで、初動の混乱を防げます。
また、事故を個人のミスとして処理せず、なぜ起きたのかを振り返り、ルールや運用を見直すことが重要です。生成AIの活用は今後も広がるため、対策も一度作って終わりではなく、継続的に更新していく視点が求められます。
ハルシネーションへの対策:まとめ

生成AIのハルシネーションは、一部の低品質なツールだけに起きる問題ではなく、現在の生成AI技術が持つ構造的な特性です。どれだけ性能が向上しても、事実確認や正誤判断を人間のように行っているわけではない以上、誤った情報が出力される可能性は避けられません。
企業利用において重要なのは、ハルシネーションを完全に防ごうとすることではなく、それを前提にした使い方を設計することです。情シスが主導して利用ルールを整理し、用途を切り分け、確認プロセスを組み込むことで、生成AIは事故を起こす存在ではなく、業務を支える補助ツールとして機能します。
今後、生成AIはさらに多くの業務に組み込まれていきます。その中で、ハルシネーションによる小さな誤りが大きな判断ミスにつながらないよう、早い段階から運用設計を整えておくことが、企業にとっての重要なリスク対策になります。